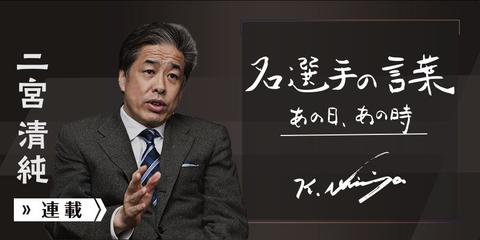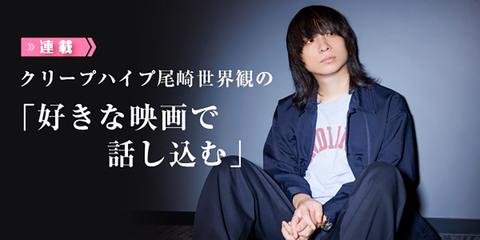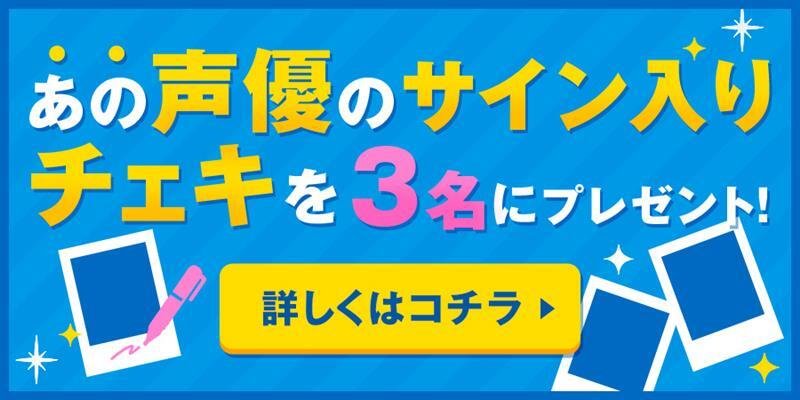声優・森田成一インタビュー#2「『幼い頃抱いた思いは間違ってなかった』独自の"ヒーロー小石論"と、その答え合わせ」
アニメ 見放題インタビュー
2025.11.21
TVアニメ「BLEACH」の黒崎一護役をはじめ、「キングダム」の信役、「FINAL FANTASY X」のティーダ役、「TIGER & BUNNY」のバーナビー・ブルックスJr.役など、数々の人気作品で主人公を務め、その力強く芯のある声と熱のこもった演技で、画面を越えて観る人の気持ちを揺さぶる森田成一さん。幼い頃に抱いたヒーローへの憧れ。そのまっすぐな思いは53歳となったいまでも変わらず、いま声優として、ようやく自身が思い描くヒーロー像に少しだけ近づいてきた、と話します。このインタビューでは全3回にわたって、森田さんが声優として歩み始めるまでの軌跡から、キャラを演じる上で大切にしていること、独自に考える「ヒーロー小石論」まで、代表的な出演作品のお話とともにお届けします。
■ヒーロー小石論

――前回のインタビューで「ヒーロー小石論」なるお話をちらっとお伺いしましたが、今回のインタビューでお聞きしたいです!
「そうそう、『ヒーロー小石論』......今でもそうなんですけど、幼い頃に夕陽に照らされたあの日から、僕はずっと『ヒーローってなんなんだろう』と考え続けてきました。そんなことを考え始める前は、『悪漢を倒し、平和を守るのがヒーローだ』と思っていたんですけど、仮面ライダー、ウルトラマン、タイガーマスク......といろいろなヒーローを見ているうちに、少しずつ自分の中での『ヒーローとはなんぞや』が変わってきたんです。往年のヒーローというのは、"善い行いをする存在だが、正体は不明である"が普通でした。そこから考え始め、中学2年生のあるときに辿りついたのが......『ヒーローは小石である』という"ヒーロー小石論"だったんです」
――ヒーローは小石である。哲学的な響きがします...!
「例えば、川に小石を投げ込むとします。投げた小石は水面に落ち、波紋ができる。その波紋が岸にぶつかると、またさらなる波紋ができる。波紋と波紋がぶつかり、また波紋ができる......。そうして川で始まった波紋の連鎖が、海に辿り着き、海を越え、他の国々へと広がっていく。海は一つにつながっているので、波紋はいつしか世界中に広がっていく。その最初の小石が、ヒーローなんじゃないかと」
――なるほど...!
「ヒーローがする"善い行い"の一つ一つは、川に小石を投げて波紋を作っているのと同じなんです。最初の善い行いが伝播してどんどん広がっていき、最終的には平和をもたらすことになる。そして、"正義"という波紋が海を渡って、それが世界に広がる頃には、つまり"正義"や"平和"が当たり前になる頃には、最初の小石はもう川底に沈んでいて、誰も見つけることができない。『この行いを始めたのは誰なんだ?』と探しても、もうわからない。正体がわからない昔のヒーローが正にそれです」
――正体不明というのも、そこにつながってくるんですね。
「日本のTVヒーローの先駆けとも言っていい『月光仮面』のオープニング曲は、こんな歌詞から始まります。『どこの誰かは知らないけれど、誰もがみんな知っている』額面通りに捉えれば、"月光仮面の正体は知らないけれど、月光仮面がいることはみんなが知っている"ということです。しかしこれを読み解けば、"正義というものが何かはわからないけれど、この世に正義というものが存在することはわかっている"ということです。それを体現し広めていくきっかけになるのが、"最初の小石"、つまり"ヒーローの善い行い"になるわけです。だからこそ『その最初の小石になることが、ヒーローになることだ』というのが、僕が中学2年生のときに考えた、『ヒーロー小石論』です。僕のすべてが、この『小石になる』というところから始まっています」
――めちゃくちゃ面白いし、それを中学2年生で思いつくのもすごいです......!
「ヒーローって、結構突拍子もない行動をするじゃないですか。でもそれって、その時代の"当たり前"に疑問を抱いて、おかしいと思うことに『おかしい』と言うからなんです。前回お話した『キングダム』の信もそうでしたよね。最初は、突拍子もないように思える"波紋"でも、広がってゆくうちに、いつしかみんなの"当たり前"になっていく。そうやって、"正義が世の中の当たり前"になっていけば良いと思うんです。だから"正義"は『なにも特別なことじゃない』んです。ヒーローの行動原理は、"みんなを守り続けること"じゃなくて、"正義が当たり前になること"だと思います」
――たしかに。ヒーローを必要としない世の中が、じつは一番いい状態ですもんね。
「そう、正義が特別視される世の中というのは、それだけ悪が跋扈(ばっこ)しているということでもあると思います」
■ありのままの自分を表現できる方法って

――森田さんは、元々俳優として活動を始められましたが、最初はどんなきっかけで俳優になろうと思ったのでしょうか?
「元をたどれば、高校時代に吹奏楽部にいたことがきっかけになりました。僕は男子中・男子高の一貫校に通っていて、高校に上がってから吹奏楽部に入って音楽を始めたんです。でもそれまで音楽なんてまったくやってこなかったから、経験も素養もない状態。じゃあ、なぜ吹奏楽部に入ったのかということなんですけど、数あるクラブの中で唯一吹奏楽部だけが、系列の女子中・女子高・商業高校と5校合同で活動している部活だったんです......つまり、女子がいたから!男子中、男子高ときて女っ気なんてまったくなかったので、ちょっと色気が出たんですよね(笑)。最初は友達に『吹奏楽部、のぞいてみようぜ』って誘われて、『音楽なんてできねぇよ』とか言ってたんですが、見に行ってそのままなし崩しに入部し......コンクールで金賞を獲るレベルの名門吹奏楽部の一員に(笑)」
――そんなにレベルの高い吹奏楽部なのに、動機が不純で笑ってしまいました(笑)。
「こればっかりはしょうがない。第二次成長期真っ只中ですから。みんな通る道です(笑)。吹奏楽部というと、皆さんが思い浮かべる、座って演奏する所謂オーケストラでの演奏もあるんですが、吹奏楽にはマーチングというのもあるんです。そのマーチングバンドを指揮する人のことを"ドラムメジャー"と呼ぶんです。当時はドラムメジャーなんて知らなかったので、『ドラムを叩く人のことをそう呼ぶのかな?』とか思ってたんですけど、入部したてで何も知らない僕にドラムメジャーの先輩が『お前、来年ドラムメジャーな』といきなりの指名(笑)。『お前は俺の下に付け』っていうことで、さっぱりわからないまま無理やりドラムメジャーの役割を覚えさせられることに」
――音楽経験もなかったのに、いきなり名門校のマーチングバンドのリーダー補佐に......。
「それからドラムメジャーの仕事を覚えていくわけですが、これがかなり面白かったんです。皆さんがイメージするマーチングバンドって、パレードで行進しながら演奏するのが一般的だと思うんですけど、海外だとスポーツの試合のハーフタイムショーなどで演奏されたり、世界的なコンクールなどもあるんです。そうした形で演奏する形式を"マーチングドリル"と呼ぶんですが、そのドリルを作るのが、ウチのクラブではドラムメジャーの仕事でした。作りたいドリルのイメージ、コンセプト作りに始まり、曲選び、構成、各楽曲に合わせたフォーメーション作り、そして実際に隊を動かしながらの演出まで、自分が思い描いたものを作り上げていく。元々、モノづくりが大好きだったんですが、音楽を通しての表現は初めて。そうしてマーチングドリルを作る中で、『マーチングという表現の中には、いろいろな要素があるんだな』と知りました」
――例えば、どんな要素が?
「音楽の要素は当然のことながら、フォーメーションには絵画的な要素、演劇的な表現など、沢山の芸術的要素があるとわかりました。そして集団芸術であることも。マーチングはまさに"総合芸術"だと思ったんです。そうこうしているうちに2年生になって、ふと『この表現を、もっと突き詰められないか』と思ったんです。世の中にはいろいろなエンターテインメントがあるけど、新たな総合芸術を生み出すことはできないかなと。そのときの考えをベースに、高校時代は"表現"について、考えていました」
――最終的にはどんな結論に?
「何かを表現するにしても、まず大事になってくるのは自分です。"自分自身"を的確に表現できなければ、何も生み出すことはできない。だから、まず"自分自身"を表現するにはどうすればいいのか、もっと言うと、できるだけありのままの自分を表現するにはどうしたらいいのかを考え始めました。表現には色々な方法があります。音楽、絵画、写真、ダンス、彫刻、文学などなど−−−。でも、それらを表現として行うには、何かを媒介にしなければならない。例えば、音楽なら楽器。それだけじゃない譜面、リズム、テンポもそう。写真ならカメラ、フィルム、印画紙、現像行程、当然被写体にも左右されます。ありのままの自分を表現したいのに、まだ自分がわかっていない僕が何かモノを媒介したら、表現したい自分が捻じ曲がってしまう可能性があると考えたんです。できるだけストレートに自分を理解し、そして表現に結びつける方法。つまりそれは、何も道具を持たず、究極は"裸"でも表現できるモノ......」
――それが......。
「そう、演技です。演技ならば裸でもできる。だから最初の興味は、芝居そのものというよりも、自己表現をするための"自分自身"を知りたかったというシンプルなもの。本当の自分は、己の奥底で何を考えているのか。そして、それをどうやったら解放できるのか。なので、目的は役者になることではなく、『自己解放の訓練』をするために始めたのが俳優だったんです」
■「卍解」でミキサーの機械が壊れた|「BLEACH」黒崎一護

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
――2026年には「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」の放送も決まっている「BLEACH」では、森田さんはシリーズ当初から主人公・黒崎一護役を務めています。
「一護といえば......実は今までに3回ほど、『卍解!』の声が大きすぎて、ミキサーの機械を壊してしまっておりまして......(笑)。音声出力のメーターがギュインッって上がったまま戻らなくなってしまって、機械をまるごと再起動......ということを3回やっているんです」
――えぇっ......それは全部「BLEACH」の現場ですか?
「アニメの現場では1回、ラジオでゲストに呼んでいただいたときに1回......。そして大阪城ホールでも......。たくさんのアーティストさんも出演されるイベントだったので、音響機材はかなりしっかりめ。そのライブの合間に、僕らが朗読劇をやることになっていて、そこで『卍解』と叫ばなきゃいけなかったんです。でもリハーサルが押してしまって、どんどん『ここは飛ばします』みたいな感じに。僕らの朗読劇パートも省略しながら進んでいたんです。でも、僕としては『卍解』があるから、『卍解のレベルゲージ、取らなくて大丈夫ですか?』と音響の方に聞いたんです。そうしたら『やらなくて大丈夫です!』と」
――危険な予感(笑)。
「でも、他の役者さんたちが『絶対やったほうがいい』とスタッフさんに伝えてくれて、『そこまで言うなら』みたいな感じで......。そのスタッフさんからしたら、なんでそこまでみんなが言うのかわからない感じだったと思うんですけど......。

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
『卍解』って全開で叫んだら、音響の責任者の方とサブの方2人が、リハーサル後、楽屋まで飛んできて下さって、『ありがとうございました!取っておいてよかったです』って御礼を言いにきたことがありました」
――森田さんの声量をみくびってはいけない、ということですね(笑)。
■失くした母への思いと、雨|「BLEACH」黒崎一護

――そんな一護ですが、森田さん自身が印象的なエピソードはありますか?
「長く続く『BLEACH』という物語に、ずっと影響している印象的なシーンは、最初期のもの。一護が母・真咲のお墓の前で、雨の中『もっと強くなりたい』と話すシーンです。あのシーンは、一護の行動原理を一護自身が語る重要なシーンです。また『BLEACH』の中では"雨"というのも、とても大切なファクターになっていると思うんですよ。雨が降れば、そのたびに一護は母を思い出し、連動してそのとき何もできなかった自分、守りたいものが守れなかった自分を思い出す。彼の物語は『自分の周りの人間は、自分で守りたい』というところから始まります。その"自分の周り"がどんどん大きくなっていく。その過程を描くのが『BLEACH』という物語です。"守る"すなわち"護る"は、彼の名前の一字でもあり、すべてはそこに繋がっていく。そう考えたとき、あのお墓のシーンは本当に大事だと思います」
――前回のインタビューでは「キングダム」の信の行動原理についてお話いただいたときに、「ヒーローや主人公を考えるうえでは、行動原理が大切」だとおっしゃっていましたよね。
「ヒーローや主人公とわかりやすく言いましたが、人間誰しも、原初体験、つまり幼少期の頃や、事の始まりってすごく重要になっていると思います。何をするにしても、自分を動かす根幹はなんだったのか、『初心に帰る』というのは、正にその始まりの瞬間の想いを辿るための言葉ですよね。そしてその始まりの瞬間には、その人の本質的なエッセンスが込められている。いろいろな道を歩くうちに、雑多なものが自分にこびりついていくものだから、多くの人は"元が何だったのか"を見失ってしまうと思います」

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
――そう言われると、自分のことのようでギクリとします。
「みんなそうだと思うんですよ。しかしそうやって漫然と生きていると、いつ間にか考えが複雑化してくる。でも実は、一番最初に思い描いたことが、一番シンプルだと思うんです。それを大事にすると"自分自身"のこともよくわかるし、自分がどういう物の見方をしていたのかを思い出すこともできる。いろいろなキャラクターを演じる上でも、最初の頃に持っていた"想い"というのは常に大事にしています」
――一護にとっては、それが母親・真咲に対する思いだったんですね。
「自分の目の前で母親が死ぬわけですから、想像を絶するほどの強烈なショックっていうのが、彼の中にはあったと思います。その後、いろいろな戦いを通じて一護は成長していきますが、その苛烈な戦いの中で、また別のショッキングなこともたくさん起こっています。でも、母親を失うほどのショック、後悔というのは、おそらく彼にとってはなかった。それを忘れると、一護は一護という人間ではなくなってしまうと思います。ですので、どんなシーンを演じるときでも、"母の死"を頭の片隅に常に置きながら、僕は一護を演じています」
■久保先生みずから直接教えてくれる|「BLEACH」黒崎一護

――森田さんにとっては、一護ってどんな人物だと捉えているんでしょうか?
「一護って実は本当にわかりづらい人物で、お芝居がしづらいんです......。それは演じ始めて20年以上経った今でも、まったく変わらないですね。彼の思考は複雑で、人の先の先の、さらに先を考えているんです。だから、一護が突然行動を起こすと、みんながポカーンとしてしまう。『なんでそんなことするの?』って。でも一護からすると、先を見据えての行動なので当然の行動なんです。だからまず、その彼の先読み思考をトレースしていかなければいけないんです。一護は表情にもそこまで思考や感情が出ないタイプなので、彼が考えていることを正確に把握するのは難しいですね。僕が『多分、こうだろう』と思ってやってみると『あれ、違う』ということも多々あって、そこで矛盾が起きると、全部が一気に崩れてしまうんです」
――言われてみると、確かに言葉も表情もけっして多いタイプではないですね......。
「そうすると、先ほどお話した『一番の根っこには、母が目の前で死んだときのこと』という気持ちに立ち返らないと、色々なシーンで一護の気持ちはこうだっていう答えに行きつかないんです。どれだけシリーズを重ねてきても、演っては立ち返り、演っては立ち返り、をずっと繰り返しているのは変わらないと思います。僕で言えば、夕陽に照らされて『ヒーローになる』という思いが湧いたあの瞬間。そこに立ち返っては今に戻り、立ち返っては今に戻り、というのをずっと繰り返している。だから、僕の人生そのものが一護とは似ているのかもしれません」
――物語の中で、つねに成長し続けている部分は、お芝居としてどんなふうに意識しているんでしょうか?

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
「元々、そんなに多弁なタイプではないですけど、『千年血戦篇』ではこれまで以上に喋らなくなっているので、彼の気持ちはどんどん読み取りづらくなっています。今までも大事な一言だけしか話さないタイプだった一護がさらに話さなくなり、今は、やっと出てきた一言が、以前よりももっと研ぎ澄まされた一言になっていくような。そこに込める想いや意味を間違えてしまわないようにするのは、かなり難しいです」
――言葉が少ないからこそ、その一言の重みが大切になってくる......。
「だから一護の芝居は、全然自分で合格点が出せないんですよ。いままで、自分で『うまくいった!』って感じたこと......ないんじゃないかな?(笑)」
――その辺は、どうやってチューニングしていくんですか?
「『千年血戦篇』に関しては、久保先生と直接会話をさせていただける機会もあって、色々と教えて下さるので、 僕たちキャストも知らないことがたくさんあって、本当に助かっています。『BLEACH』は久保先生が本当に色々な伏線を貼っていて、後々にならないとわからないことがたくさんあるんです。原作からでは読み解けなかったことも、久保先生から直接教えて頂くことで物語全体の解像度が上がるんです。中には『もうちょい前に教えてよ!』と思うこともあるんですけど(笑)」
――(笑)。
「『BLEACH』に限らず、他の作品に関してもそうなんですが、僕は基本的にあまり先を知りたくはないんです。『BLEACH』の原作は完結していますが、久保先生が原作では描かなかった部分を解釈して、アニメで描いている、という風に僕は感じています。知らないことがたくさんある『BLEACH』ですが、演技プランを立てるにしても、前々からわかって準備するより、その瞬間に理解し、ファーストインプレッションでお芝居をする方が、新鮮で生き生きしたものになる場合もあります。だから、『BLEACH』のスタッフさんにも『僕には先の展開を教えないでください』とお願いしているんです(笑)」
――そうだったんですか!
「どうしても知らなきゃいけないことだけは教えて、それ以外は教えないでほしい、と。実際、制作会議の中で、物語としての大事な設定を『森田さんに伝えるかどうか』と、議題に上がることもあるらしいです(笑)。そうすると、久保先生が『これは森田さんには教えないほうが良さそうだね』というふうにおっしゃることがあるみたいで......。作品としても長くなってきたし、僕にどんなクセがあって、どういうお芝居をするのか、スタッフの方々もよくわかっています。そこは手綱を握ってもらう形でやっています」
■ときどきやらかす、大先輩・菅生さん|「BLEACH」黒崎一護

――森田さんから観た『千年血戦篇』での思い出や印象深いことがあればお聞きしたいです。
「物語の内容ではないですが、『千年血戦篇』第1クールの1話目、久しぶりにあの『BLEACH』が帰ってきたんだ、というみんなの期待と興奮を感じたときですね。配信ではなく地上波のテレビ放送で、毎週決まった『この曜日のこの時間』という形で放送を再開できたことにものすごく感動しました。1話目では現世メンバーが勢揃いしたり、アニメシリーズとしては久々に『卍解』と言えたり、本当に嬉しいことだらけでした。小さな頃から『BLEACH』を観て育った人たちが大きくなり、今や大人になってる方もいて、『これを待ってた!』『まさかまた観られるなんて!』というふうにも言っていただけたりしたんです」
――それは嬉しいですね。
「しかも現代の技術で作られているから、クオリティが劇場版と見紛うくらいだし、こんな最高の状態でみなさんにお届けできるようになったのは、作り手の一人として大きな喜びです。また、『BLEACH Brave Souls』というゲームのおかげで、アニメが放送していない期間も、僕達キャストはキャラクターの声を出し続けていられました。おかげで途切れることなく、自分の役とともに歩いてこられた感覚がずっとあります。それは、僕だけじゃなくてキャストみんなが口を揃えて同じことを言っています。でもゲームは基本的に一人で収録するので、久しぶりにアニメ収録で全員揃ってアフレコをしたときは、みんな懐かしがって......。それもすごく楽しかったなぁ」
――何かアフレコならではの思い出があったり?
「最近ありましたね。事件というか個人的にショッキングな出来事が。現場では、ユーハバッハ役の菅生さんと一緒に収録する機会が多いんです。菅生さんといえば、アニメのみならず、舞台、映画、ドラマ、海外映画の吹き替えなどでも数多く大活躍されている大先輩。で!僕は今、某配信サービスで放映している海外ドラマにハマっているんです。その作品に菅生さんが吹替でご出演されていたんです。まだ2話目の途中までしか観ていない状態だったのですが、それでもすごく面白かったので、菅生さんに現場でお伝えしようと思って」
――なるほど。
「『BLEACH』の収録のときに、『あの作品めちゃくちゃ面白いですね!』って菅生さんにお伝えしたら、『おう、ありがとう!まさか自分が犯人だとは思わなかったよ』と」
――(爆笑)。
「自分から話をふった手前、さらには大先輩。何も言えずその件については触れませんでした。現在は、すでに犯人がわかっていながら観るという地獄のような状態です。それでも作品はすごく楽しいんです!物語の展開がハラハラワクワクなので、楽しんで観ています。むしろ、犯人を知りつつ、どうなったらこの人が犯人になるんだ?いやいや絶対にコッチの方が犯人ぽいでしょう!などと頭を捻りながら、新しいミステリーの見方を堪能しています!」

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
――(笑)。なごみますね、菅生さんの存在。
「菅生さんは役者として様々な経験をされていらっしゃいますから、一緒に現場に入ると本当に興味深いお話をたくさんしてくださるんです。もちろん笑い話やピンチだった話も。すごく勉強になります。でも時々そうやって面白いことをされるので、自然と愛すべき人物になっていってますね(笑)」
■ヒーローになるには、50年かかる|「BLEACH」黒崎一護

――「BLEACH」は日本だけでなく、海外でも愛される作品になっていますけど、それを実感することもありますか?
「年々その実感は増していますね。特に一番感じたのは、3年前にアメリカに行ったとき。コロナ禍で、向こうでも大きなイベントが数年全然できていない状態だったんですが、久しぶりに北米で大きなイベントがあったんです。そのイベントのサイン会でのこと、僕の前に『会いたかった』と泣きながらやってきた方がいて...。ものすごい巨漢。身長2m以上あるんじゃないかという筋骨隆々の方が、僕と握手して泣いているんです。すると震える声で『僕はあなたの「BLEACH」を観て、育ったんだ』って」
――海外ファンの熱量もかなり高いんですね。

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
「その方が言うには、『子供の頃に「BLEACH」を観て、人を守るということが何かをずっと考えてきた。それを学ばせてくれたのが、あなたなんだ。そして今、私はファイアーファイター(消防士)になった』と。ファイアーファイターというのは、アメリカでもものすごく尊敬されている職業なんです。『BLEACH』から学んだことを活かして、人を守る職業に就いたということに、とても感動しました」
――めちゃくちゃいい話......。
「そういう方が他にも数多くいて、 『BLEACH』の影響で警察官や看護師になったという人たちが大勢会いにきてくれたんです。そのときに、僕は自分が考え、そして実践してきた『ヒーロー小石論』が、ようやく現実になったと思いました。自分が投げた小石の波紋が50年をかけ、太平洋を越えてアメリカに辿り着いたんだと。それだけじゃない。アメリカの『BLEACH』ファンからもらった声は、波紋になってまた僕に返ってきた。長い時間がかかったけど、幼い頃に抱いたヒーローへの憧れ、そしてどうすればヒーローになれるかと考えたことは、けっして間違っていなかった」
――ここで『ヒーロー小石論』に繋がってくるとは......!
「"ヒーローの善い行い"は、たとえ目の前に大きな海、大きな隔たりがあっても、必ずそれらを越えて広がっていくんだということがわかったのは、素晴らしいことでした。それに、それを死ぬ前に確かめることができたのは、とてもありがたかった。日本でも、『BLEACH』や『キングダム』、『FINAL FANTASY』などを『観ました』『やっていました』と言っていただくことも増え、中には一緒に仕事をする方々も現れた。そしてその方々と共に、新しい作品を作ることができている。波紋は、確実に僕に返ってきているんです。"波紋"というヒーローになるには、50年かかるんですね。3歳の頃に考えたことが、53歳になる今にまで繋がってきたことが、僕にとってこれからの生き方を考える上でも重要になってくると思います」

取材・文/郡司 しう 撮影/梶 礼哉