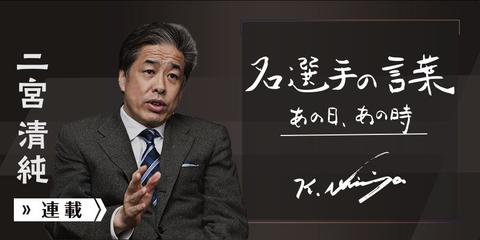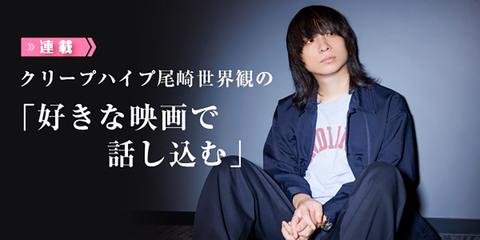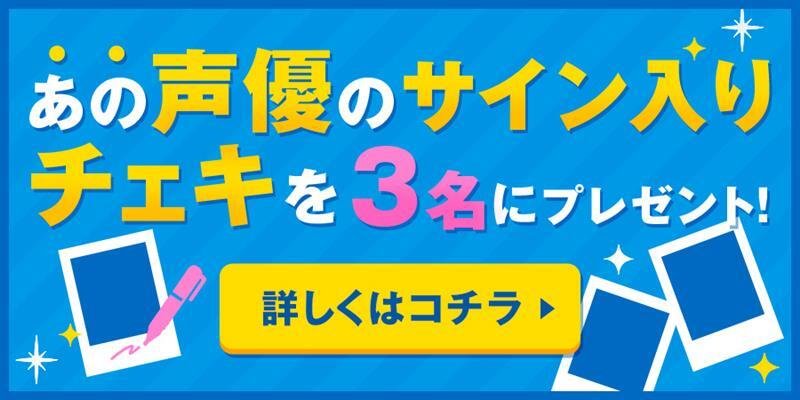映画『国宝』の名演にもつながる『ぼくが生きてる、ふたつの世界』吉沢亮のディープな役作り
2025.10.04
公開中の映画『国宝』(2025年)が興行収入150億円を超え、"22年ぶりとなる邦画実写映画での100億円超え"、"映画『南極物語』(1983年)を抜いて歴代邦画実写映画興行収入ランキング第2位(※9/24現在)"と歴史的快挙を成し遂げ、その勢いはまだまだ続きそうだ。同作品は、吉沢亮演じる任侠の家に生まれた主人公が歌舞伎に人生を捧げ、女形として人間国宝に上り詰めるまでを描いた人間ドラマ。"邦画実写としては破格の10億円を超える製作費"、"1年半にわたる歌舞伎の猛稽古"なども話題だが、中でも主演の吉沢と共演の横浜流星の好演が評判になっている。そんな"国宝級"の演技を披露している吉沢が、同作に勝るとも劣らない演技を見せている作品が映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』(2024年)だ。本作は10月5日(日)に日本映画専門チャンネルで放送される。
「コーダ」の青年の成長を繊細に描き出す
この作品は、五十嵐大による同名自伝的エッセイを原作に、"耳がきこえない、またはきこえにくい親を持つ聴者の子供"=「コーダ」の半生を描いた、切なくも心に響く家族の物語。吉沢は主人公の五十嵐大に扮(ふん)して、"きこえる世界"と"きこえない世界"を行き来しながら生きる青年を体現し、自身の居場所を見出していく若者の心を繊細に演じている。
宮城県の小さな港町に暮らす五十嵐家に、男の子が生まれる。祖父母、両親は、その子に「大」と名付けて誕生を喜ぶ。だが、他の家庭と少しだけ違っていたのは、両親の耳がきこえないことだった。幼い大にとっては、大好きな母の通訳をすることも普通の楽しい日常だった。しかし、時が経つにつれ、周りから特別視されることに戸惑い、いら立ち、母の明るささえも疎ましくなる。心を持て余したまま20歳になった大は、逃げるように東京に旅立つ、というストーリー。

主人公の心の成長を丁寧に表現
映画『国宝』にも通ずるが、吉沢の演技は「ある人物の半生を演じさせたら、右に出る者はいない」というほどに群を抜いている。反抗期特有の"周りのことに全ていら立ってしまう様子"や"変わりたいのに変われないもどかしさ"を瑞々しく演じたかと思えば、青年となって精神的に成長した様子を生き生きと表現し、自立して一人の大人として母と向き合えるようになってからの柔和な様子を、習熟した演技で巧みに表すという"7色の変化"で役の成長を描き出している。

芝居の細部に宿る深みのある役作り
これは、彼の深度のある役作りの賜物であろう。吉沢といえば、映画『国宝』での1年半に及ぶ歌舞伎の稽古や、大河ドラマ「青天を衝け」(2021年、NHK総合ほか)での8kg増量といったエピソードが挙げられるように、過酷とも言える驚異の役作りを経て役に没入する本格派。自身の魂を削りながら"役に成って"いくのだ。
同作でも、手話を使いながらの感情表現で、その深みを感じることができる。小さい頃から母とのコミュニケーションは手話であるため、「手話ができる」というレベルではなく「自然に出てくる」というレベルに達している必要があるのだが、激昂した場面など気持ちが高ぶったシーンでは、口調だけでなく手話までも粗雑になっており、より感情が伝わってくる。自身も「実際に手話で生活されている人たちの使う手話のレベルでの演技はすごくハードルが高かった」とコメントしているが、意識的に雑に動かすと作為的に見えてしまうため、考えて動かすのではなく、体に染み込ませていないとできないリアルさだ。
同作で役の各年代での心の機微を丁寧に描き、滑らかなグラデーションで成長を描き出す吉沢亮の名演に触れて、彼のディープな役作りを感じてみてほしい。
文/原田健