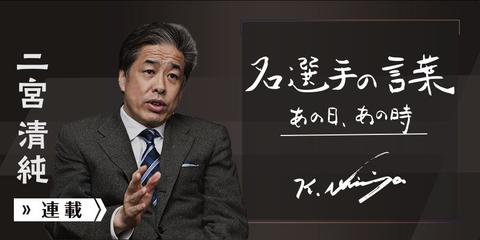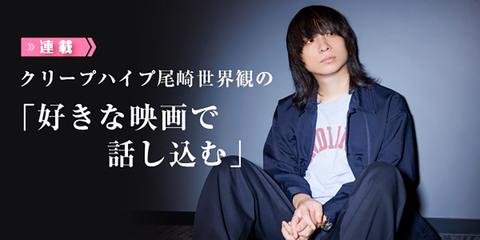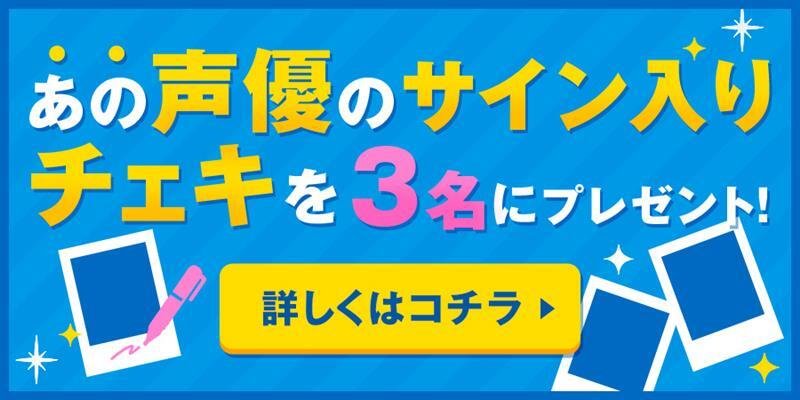声優・森田成一インタビュー#3「声や喋り方以上に、いかに新鮮な表現ができるかが大事」
アニメ インタビューレンタル
2025.11.28
TVアニメ『BLEACH』の黒崎一護役をはじめ、『キングダム』の信役、『FINAL FANTASY X』のティーダ役、『TIGER & BUNNY』のバーナビー・ブルックスJr.役など、数々の人気作品で主人公を務め、その力強く芯のある声と熱のこもった演技で、画面を越えて観る人の気持ちを揺さぶる森田成一さん。幼い頃に抱いたヒーローへの憧れ。そのまっすぐな想いは53歳となった今でも変わらず、声優として、ようやく自身が思い描くヒーロー像に少しだけ近づいてきた、と話します。このインタビューでは全3回にわたって、森田さんが声優として歩み始めるまでの軌跡から、キャラクターを演じる上で大切にしていること、独自に考える『ヒーロー小石論』まで、代表的な出演作品のお話とともにお届けします。
■NHKプロモーションアクターズゼミナールのOB会へ

――前回のインタビューでは「自分自身のことを表現する方法を知るために役者になった」というお話をお聞きしました。
「そうです。人って自分自身の奥底で何を考えているのか、本当の所はわからないじゃないですか。その本当の自分を知って、自分自身を解放することが自己表現の糸口になるんじゃないかと思って始めたのが俳優でした。『NHKプロモーションアクターズゼミナール』の門を叩いて、いきなりオーディションを受けに行ったんです。今考えるとお芝居もやったことなければ、表現者として何の根拠もない自分が、『絶対受かる』と思ってオーディションを受けに行ったのは恐ろしいですよね(笑)」
――逆に、前しか向いていないからこそ、まっすぐ進んでいけた部分もありますか?
「意識はしていなかったですけど、そういう部分はあるかもしれないですね。あの自信は、どこからやってきたんだろうと今は思います。その時に入った『NHKプロモーションアクターズゼミナール』はちょっと特殊で、基礎科、本科、声優科に分かれているんですが、メインはそこではなく、卒業後に所属できるOB会なんです。実はそこまで辿り着くのが大変なんです。基礎科に入るためにまずオーディション。基礎科から本科に進むためにオーディション。そしてOB会に所属するためにオーディション。そのOB会のオーディションがとにかく狭き門で、普段のレッスン時の演技レベルを数ヶ月前からずっと審査され続け、その後、講師陣全員とOB全員のOKがないと合格できないという......」
――かなり、狭き門ですね。
「『NHKプロモーションアクターズゼミナール』は、いわゆる養成所や学校のようなところではなく、すでに演技人として仕事をしているプロ達が、さらにレベルアップするために集まる現場直結の"稽古場"なんです。厳しくふるいにかけるのも、"プロの稽古場"としての高いレベルを下げないためのシステムなんです。本科のレッスンにも同様のものがありますが、NHKの現役ディレクターやプロデューサー、舞台演出家、映画監督が講師として招かれる『ディレクターズタイム』というレッスンがあります。稽古では、稽古で使用する台本を自分たちで集め、精査し、そこから決定した台本を使用します。講師のディレクターや監督が実際、過去に演出された作品をやることもあります。その台本を使用して稽古をするのですが、ここからが普通の稽古と違うところ。従来通りの、まず演じる役を決め、一つ一つのシーンを丁寧に稽古していくやり方ではなく、講師が「お前はこの役、お前はこの役......』とその場で役を割り振られます。そしてぶっつけでお芝居をするんです。台本は事前に配られていますから、覚えることはできますが、どの役が振られるかはわからないので、全て対応できるように全て覚えます。しかしどの役が振られるかはわかりませんし、相手役も誰かはわかりません。ですので事前の合わせ稽古というのはできないんです。あくまでも、各自が持っている演技力、アイデア、センスなど、全てのポテンシャルのみで芝居を成立させることが求められます。衣装や小物なども各自で考え用意するんです。台本を正しく理解し、さらに自分の解釈を導き出すんです。それを役者としていかに柔軟に、瞬間的に対応し演技ができるかが試されるんです。そして同じ役を他の役者さんも演じるので、他者との、演技や芝居に対する考え方や感じ方などの違いを知ることもできました。これはとても勉強になることでした。そして稽古が上手くいけば、そのままドラマの役をもらって現場に連れて行ってもらえる。つまりプロとして"仕事"ができるということです。」
――稽古がそのまま、オーディションになってるんですね...!
「ちなみに、僕らの代で本科から数人一緒にOB会へ上がった仲間たちがいるんですが、その仲間たちで出演したのが、『FINAL FANTASY VIII(以下、FFVIII)』でした」
■自分たちで演出も付けたモーションキャプチャー(FFVIII)

――そうだったんですか...!
「正確には、同じくNHKのOB会の先輩が1名と、青年座の方がお一人いらっしゃいましたが、あとは全員が同期でした。当時は、モーションキャプチャーを使っているゲームなんてなくて、当時のSQUAREさん(現SQUARE ENIX)のほうでも、どういう人をモーションキャプチャーアクターに起用すれば良いか探り探りだったようです。オーディションにはモデルやダンサー、パントマイムの方など、ありとあらゆる表現者が受けていたらしく、その中でオーディションに通ったのが僕たちでした」
――たしか『FFVIII』では、熱血タイプの格闘家・ゼルのモーションキャプチャーをご担当されたんですよね。
「ゼル以外に、実は主人公のスコールもオーディションで受けていました。小さい頃から剣道を、大きくなって空手をやっていたので、剣士も格闘家もどちらでもいけると思って。実際、モーションキャプチャーだと顔は映らないので、シーンによってはスコールを演じている場面もあるんですよ」
――スコールもやっていたとは! そのモーションキャプチャーは、どんなふうにして進められていったんですか?
「『FFVIII』時代には、まだゲーム自体に声が収録されていないんです。つまり、僕らが演じるのはキャラクターの動きのみ。とはいえ、登場人物のリアルな感情や動きを表現するためには、セリフはとても重要な要素。なので僕らはセリフをすべて覚えて、その場面の芝居をしながら動きを付けていきました」
――え...!声が入らないのに、全部セリフを覚えたんですか!?
「そうでないとキャラクターに生きた感じが出ませんからね。ただ、ゲーム業界と芝居の業界ではいろいろな常識が違います。当時のSQUAREさんも初めての試みで、最初は手探りなことばかりでした。なにしろ初めの頃は、台本らしい台本すらありませんでしたから。プログラムの指示書みたいなものがあるだけで、僕らが見てもどれがセリフなのかもわからないくらいだったんです。しばらくしてSQUAREさんから「台本ってどういうものですか?」と聞かれ、当時のマネージャーが、NHKの連ドラの台本を持っていって『これが台本です』と。そこで初めて、SQUAREさんも台本の形式がわかる、みたいな感じです」
――そういう意味ではゲーム業界でもパイオニアだったんですね。
「そうだと思いますよ。もう一つ、畑違いならではの話があって、最初の頃は僕らがどんな演技をしようと必ず一発でOKが出ていたんです。これは後に、プロデューサーさんが別のインタビューでお話しされていたと思うんですが、実際に僕らの演技をどう見たらいいのかわからなくて、全部OKを出していたそうなんです(笑)」
――なんと(笑)。
「ふだんの稽古場だと、そんなことはあり得ないんです。必ずダメ出しが飛んでくるし、『これでいいよ』なんて言われることはまずないので、ダメ出しがないことが逆に怖くて(笑)。でも、そうなると人間は自発的に考え始めるもので、「このままだと全部一発OKで、失敗してても、その姿を世界中の人に晒すことになる。それはマズい」と僕ら俳優側がみんなで話し合って、演出プランを自分たちで考えるようになっていったんです」
――めちゃくちゃ面白い話ですね...!森田さんの動きが見れるかと思うと、久々に『VIII』プレイしたくなりました。
■ティーダはそっくりそのまま自分(FFX)

――ちなみに、『FFX』のお話もお伺いしていいですか?
「もちろんです。『X』のときも、じつは『VIII』からほぼそのままのメンバーで『モーションキャプチャーお願いします』と。『Ⅷ』などの経験があったので、みんな勝手がわかった状態で望めました」
――あれ、でもたしか森田さんは主人公・ティーダの声も担当されていますよね?
「そうなんです。ご存知の通り『FINAL FANTASY』は『Ⅹ』からキャラクターボイスが導入されています。そのキャラクターボイスのオーディションも同時進行で行われていました。でも、なかなかオーディションで決まらなかったようです。1回目のモーションキャプチャー収録のときに、プロデューサーの方から『まだ声のキャストが決まっていないんです。でもこれ以上遅れると、制作が間に合わなくなるので先にモーションキャプチャーだけ撮り始めます』という話でした。そして1回目の収録を終えたところで、プロデューサーから『森田くん、今度本社に来てくれる?』って言われて。やばい、俺なんかやらかしたかな、と」
――呼び出しをくらった、みたいな(笑)。
「その呼び出しの日。本社に伺うギリギリの時間まで、僕は友達とボウリングをやっていたんです。『どうせ怒られるなら、ちょっとでも楽しい思いをしとこう』って考えて(笑)。そしてボウリングを一旦抜けて、SQUARE本社に行くと、応接室みたいな大きくてすごい会議室に通されたんです。部屋にはすごーく長いテーブルがあって、その真ん中にプロデューサーが、対面に僕が座りました。僕は『きっと、この長いテーブルに偉い人がずらっと並んで全員から怒られるんだろう』と思ってドキドキしていたら、プロデューサーがカメラを回し始めて、紙を一枚渡され、『これ、読んでみて』と。何かヤバい通告の紙で、クビの瞬間でも撮影されるのか......と思ったら、ティーダのセリフが書いてあったんです(笑)」
――やっとひと安心(笑)。
「ええ。『怒られるわけじゃなかったのか。今後の撮影の為の資料かな?』と思いました。ティーダのセリフを読み終わったら、『帰っていいよ』と。その足でまた友達のところに戻ってボウリングの続きをバッチリ楽しみました!みんなに『怒られなかったー!』って言って。そうしたら後日、『ティーダの声に決まりました』と正式にSQUAREさん側からオファーを頂きました。まさかこの間の一件が、オーディションだとは全く思わなかったのでびっくりしましたね。ティーダのキャラクターボイスは、スタジオではなくて会議室で決まったんです(笑)」
――ティーダを演じるにあたっては、どんな役作りをしていったんでしょうか?
「これまで、声優としてティーダの他にもいろいろな役をやらせて頂いてきましたけど、ティーダに関してだけは、僕は全く役作りをしていないんですよ。"生声"という意味ではなく、彼の性格や思考回路が、そっくりそのまま僕と同じなので、唯一ティーダだけは、ティーダ専用に作り上げた演技をしていないんです。ですのでティーダは『特別な存在』だと思っています」
■どこか欠落した"人間サイズ"のヒーローたち|「TIGER & BUNNY」バーナビー・ブルックス Jr.

(C)BNP/T&B2 PARTNERS
――2022年のSeason 2の放送以後、いまだにファンから根強い人気がある「TIGER & BUNNY」。森田さんはバーナビー・ブルックス Jr.を演じていらっしゃいましたが、どんなことを意識されていましたか?
「そもそも『TIGER & BUNNY』という作品は"ヒーロー物"でありながら、完全無欠のヒーローがおらず、登場するのはどこか欠落した部分を持つヒーローばかりですよね。その"人間サイズ"のヒーロー像がすごく面白いところで、みなさんが夢中になって観ているのも、そういう描き方に魅力があるんじゃないかと思っています。その中でバーナビーは、両親を亡くしているという悲しい過去を持つキャラクターとして登場します。彼の歪みは、自分の顔、実名をさらけ出し、自分をおとりにしてまでも犯人を呼び寄せようとしている、その復讐心。そういう想いを持ったところが、やっぱり"人間サイズ"なんですよね。ですのでバーナビーを演じるときは、彼を"ヒーロー"だとは思わないようにしていました」
――人間らしい部分を大事にしている、ということでしょうか?
「そうですね。"自分をおとりにする"というのは、現実ではそうあることではないですが、"仇を討つ"という側面から考えると、とても"人間臭い"行動だと思います。ですので、"正義を貫くヒーロー"感を強く押し出すことよりも、"人間・バーナビー"を表すことに力点を置きました。その他でとても気を付けたことは、他の登場人物との距離感です。たとえば、ヒーローとしてオーディエンスに話す時、虎徹以外のヒーローと話す時、独り言を呟いている時、そして虎徹と話している時も、『おじさん』と話しているのか、『虎徹さん』と話しているのかで喋り方が変わってくる。関係性や立ち位置によって細かく変わってくるんです。つまり彼の中ではその喋り方に明確な理由があるんですよ。それらを整理しながら演じ分けていかないと、整合性が取れなくなってくるので、演じる上でかなり意識したポイントだと思います」
――確かにわかりやすい部分では、その時々と状況で虎徹との距離感が明らかに変わってるのが伝わってきますね。

(C)BNP/T&B2 PARTNERS
「そう。バーナビーは人との距離感が行きつ戻りつするので、『おじさん』呼びが『虎徹さん』になるまでにもすごく時間がかかったし、そもそも『おじさん』の言い方でも、距離感によって変わってくる。虎徹をはじめ、他のキャラクターとの距離感がミリ単位で変わってくるので、その距離感を正確にとらえたり、考えたりすることに神経をすり減らしていました」
――バーナビー自身の性格はどんなふうにとらえていますか?
「元々は、きっと明るいだろうし、優しい人だと思います。状況が許せば、ちゃんと仲間とも打ち解けられるし、輪にも入っていける。ただ、自分からの出し方がまだよくわかってないんでしょうね。それができないのは、幼少期の頃の体験が大きいんだと思います。自分を隠したり、無意識に人と距離を取って接するというクセがついてしまっている。だから、それを無理やりこじ開けにくる虎徹を最初は冷たくあしらってしまう。その壁の作り方は、僕も幼少期にすごく引っ込み思案だったので、バーナビーを演じる上ではその頃の自分の気持ちを利用したりもしています」
■「古いな」というセリフで彼のことが好きになった|「TIGER & BUNNY」バーナビー・ブルックス Jr.

――森田さんの中で、思い出深いエピソードやシーンなどはありますか?
「最初の頃から言っていたことではあるんですが、彼のセリフで一番好きなのが、第1話で虎徹に向かって『古いな』と言う一言。あの一言は、当時、本当に斬新でシビれました。現役でヒーローをやっている人に対して、一言『古いな』としか言わないんですよ? あんな言い方をしたキャラクターってこれまでいないんじゃないかなと思うくらい。素晴らしい!あんなにエポックメイキングなセリフはないと思います。あの瞬間に、僕はバーナビーのことが好きになりました」
――ちなみに、実際にお芝居をするときにはどんな意識でその言葉を言ったんですか?

(C)BNP/T&B PARTNERS
「もう、本当にクールに。とにかく冷たく残酷に。そして冷笑しつつ、ぼそっという感じを表現したくて。短いセリフだけど『このセリフで、バーナビーのアイデンティティが全部決まる』という気持ちでやっていました。とか言っていますが、実は元々バーナビーは受かると思っていなくて......。演じるなら、もう一つ受けたスカイハイの役が自分には合っているだろうと思っていたんです。『バーナビーは、もっと若い声優さんがやるだろう』って勝手に思ってて(笑)」
――森田さんのスカイハイも、それはそれで見て見たいですね...!(笑)
「スカイハイって、2回同じこと言うじゃないですか。あれ、面白いですよね。あれを見て、『これこれ!これは俺だろう!』とか思っていたら、まさかのバーナビーでお役を頂くことになって。『ありがとう!そしてありがとう!』は言ってみたかった......!でも、そんな気持ちで現場に入ってから井上剛くんのスカイハイを見たら、『あ、これが本物のスカイハイじゃん』って。なぜ自分がスカイハイに選ばれなかったのかを一瞬で理解しました(笑)」
■新鮮な表現は、距離感から生まれる|「TIGER & BUNNY」バーナビー・ブルックス Jr.

――Season 1とSeason 2の間には11年間もの間がありましたが、ブランクは感じましたか?
「そうですね、Season 2の最初の日、虎徹役の平田さんと一緒に、音響監督から言われたのが『もっと若く!』だったんだよなぁ。時というのは残酷ですよね。その言葉で、ふたりでズゥン......って沈んでしまって(笑)。まず、そんな強烈な一撃を喰らいながら始まったのがSeason 2でした」
――(笑)。
「それと、こうして間が長く空いたときに怖いのは、そのキャラクターから離れている間に、『自分の中でキャラクターが醸成されてしまっている』ということなんです。例えば、シーズンとシーズンの間が空いたときに、その合間にゲームの収録があったり、イベントなどでファンの前でセリフを言ったりする機会があると、一部だけ抽出された人気のセリフを何度も言うじゃないですか。そうすると、徐々に自分の中でのキャラクターイメージが固まっていってしまったり、お客さんの求めるキャラクター像に近づいてしまったり、少しずつ変化してしまうんです。それをそのまま次のシーズンに持っていくと、変に醸成された状態のものになってしまう。例えば、バーナビーで言えば、『行きますよ、おじさん』っていうのばっかり言っていたら、その言い方が、だんだんと"型"になってきてしまうわけです。でも、実際には『おじさん』の喋り方や熱量にも何パターンもあるし、その状況に合わせた言葉を出せなければお芝居はできない。型になってしまうのは恐ろしいことです」

(C)BNP/T&B2 PARTNERS
――なるほど...!
「前回お話しした『BLEACH』だって、アニメが放送していないときでも、ずっと『卍解!』って叫んでますからね。余談ですけど、おそらく僕が人生で一番喋ってる言葉は『卍解』だと思います(笑)」
――(笑)。でも、そういうときはどうやってリセットするんでしょうか?
「僕がよくやるのは、『あえてそのキャラクターに対して冷たくする』ことですね。『TIGER & BUNNY』ならバーナビーに対して。Season 1では、ガーッとバーナビーとの距離感を詰めたんですが、Season 2では『もう見てやらん!』みたいな状態にしました。キャラクターとの距離を意識的に遠くし、そこからお芝居をすると結構うまく行くことが多いんです。特にバーナビーの場合、彼自身がクールでツンとしている部分があるので、そういうやり方が活かしやすかったですね。」
――キャラとの距離感が近づきすぎるのは、よくないんですか?
「近づきすぎても、遠ざけすぎても良くないと思います。バーナビーでいうと、Season 1とSeason 2の合間に、ゲームやイベントを通じて、僕とバーナビーとの関係性がより強くなって、より距離感が近づきました。一見すると良いことなんですが、そうすると、バーナビーと森田の間の距離感があったからこそ生みだすことができた相互の理解がなくなってしまうんです。僕自身の感覚なのでわかりづらいと思いますが、それはまるで『固く強いが、異様で不気味な塊』のような感じで、それが僕とバーナビーの中に居座ってしまう。そうなったら一度それを壊して、力技でも距離を作らないと、なかなか元の関係に戻ってくれないんですよ。でもその作業も結構大変で、どの部分が後からくっついてしまった物なのか、自分で判別するには時間と労力がかかるんです。でもキャラクターとの関係性を正しい状態にするためにはとても大事なことです」
――その部分を一度客観的に見直すために、あえて遠ざけるんですね。
「そうです。自分のイメージとか、ファンが求めるキャラクター像とか、いろいろなものが乗っかってしまっているから、一度離れて、それを一度シンプルに捉え直すんです。世の中に長く続く作品はたくさんありますが、役者の皆さん、本当に苦労される部分なんじゃないかと思います。声優がキャラクターに慣れてしまうと、そのキャラクターは死んでしまうと思います。どうやったら、常に新鮮な状態でそのキャラを表現できるか。そのせめぎ合いは先輩たちのお芝居からもたくさん学んでいます」
――つねに新鮮な表現をするために意識すべき部分が、キャラとの距離感なんですね。
「はい。声優というと、"良い声や喋り方のプロ"だという印象を皆さんお持ちかもしれないですけど、それ以上に僕らが重要視するべきなのは、新鮮な表現だと考えています。もしバーナビーの『おじさん』が一つの言い方の型にハマってしまったら、それはもう死んだ言葉です。わかりやすくいえば、"声をコピペ"している感じ。そうではなく、置かれている状況があって初めて出てくる『行きますよ、おじさん』は、どういう意味なのかを考えて声を、いや"言葉"を発さなければ、つねに新鮮な表現はできない。そういう言葉は、声優とキャラクターとの関係性、距離感の中で生まれるものだと思います。近すぎて馴れ合いすぎてもダメだし、遠すぎて気持ちが重ならならないのも違うんだろうなと思います。そして、そういったキャラクターの思考法や行動原理、距離感などを意識的に準備する作業を全く必要としないのが、『FINAL FANTASY X』の『ティーダ』なんです。だから『ティーダ』は特別なんです。」

取材・文/郡司 しう 撮影/梶 礼哉