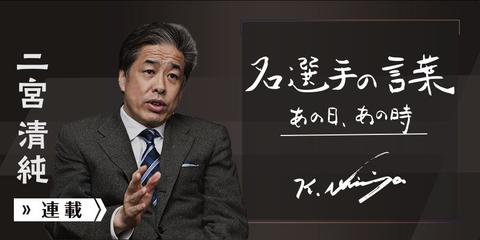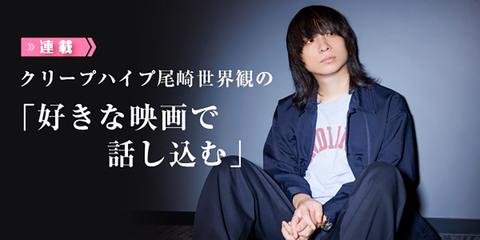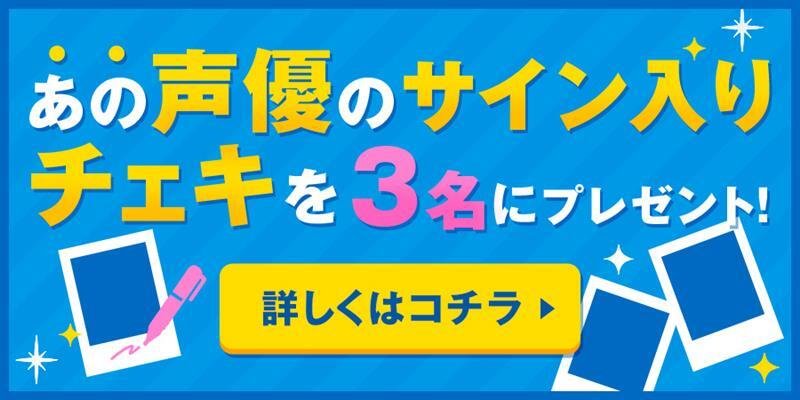声優・堀江瞬インタビュー#2「キャラクターと心を重ねることができたあの一瞬を、いまでも追い求めている」
アニメ 見放題インタビュー
2025.08.22
「原神」の空(男主人公)、「僕の心のヤバイやつ」市川京太郎、「彼女、お借りします」の木ノ下和也など、数々の人気作品で主演を務め、"ホリエル"の愛称でも親しまれている声優・堀江瞬さん。ですが、実は元々、自分の声が高いことがコンプレックスだったと言います。そんな彼がどうして声優を志したのか、そしてその過程で培っていった「余白」を持つことの大切さとは。このインタビューでは、全3回にわたって声優・堀江瞬の人となりと素顔に迫ります。
■バイト時代のリアルな経験が声優業の礎に

――前回のインタビューでは大学時代、養成所の学費を稼ぐためにアルバイトをしているとお聞きしました。どんなバイトをしていたんですか?
「カラオケ店で夜勤のアルバイトをしていました。大学1年生のときからサークルにも入らず、本当に週5~6日働いていたんですが、なんなら大学よりも"自分の居場所"を見つけられた感じがして、バイト仲間にも恵まれ、すごく楽しく働かせていただいていました。夜勤で働く仲間は同世代も多かったので、シフト後に事務室でやさしいパートのおばちゃんが握ってくれたおにぎりを食べながら、みんなで喋ってる時間がすごく楽しかったな。気軽にいろんなことを話し合える仲間との、そういう何気ない時間が、当時の僕にとっての小さな居場所だったのかな、って思います」
――いい仲間に恵まれた職場だったんですね。
「そうですね。養成所に通い始めたり、オーディションに受かるようになってからも、そこでアルバイトは続けていましたし。同時に大学にも通っていたので、朝はアフレコ、夕方に大学で授業を受けて、夜はカラオケ店で夜勤のバイト......と、いま思うとかなりハードな毎日でした。いま、同じ生活をしろと言われたら、絶対に無理だと思いますが、当時は血気盛んで気持ちがトガっていたし、モチベーションとかバイタリティがものすごかったんですよ(笑)。養成所でも『誰にも負けない』『絶対、俺が声優になってやる』って周囲に対する闘争心も強かったので、そんなハードな生活も苦にならずに続けられていたんだろうなぁと思います(笑)」
――堀江さんにも、トガってる時代があったとは意外です......!
「もちろん、その闘争心も自分の心の中だけで燃え上がっているものなので、面と向かって周りに言ったりもしないし、それが伝わるような態度はとっていなかったつもりですが......自分の中では勝手にトガりにトガって、本当に技術も何もないのに、気持ちだけは誰よりも強かったと思います。いまはよくも悪くも、そういう気持ちが削ぎ落とされてしまったなぁ(笑)」
――誰しも、年を重ねると丸くなる部分はありますよね(笑)。ちなみに、カラオケバイトを通してはどんな学びがありましたか?
「アルバイトを通して学んだことは、すごくたくさんあると思います。僕は5年間、同じ場所で働いて自分で稼いだお金で自分の生活をまかなっていたので、それ自体がすごくいい経験でした。お金の価値や、社会に出る上で最低限持つべき価値観みたいなものは、アルバイトで学んだような気がします。声優に関することは養成所で学んでいましたけど、そうじゃない人間的な過ごし方の部分はアルバイトのほうが多くの学びがあったんじゃないかな」
――いわゆる、学校では教わらないような社会生活的な部分ですね。
「そうそう。やっぱり若い頃のアルバイトって、社会生活の最初の一歩じゃないですか。社会性や人間関係に関しても、家庭や学校よりも大きな学びがありましたよね。それまでは家や教室の中がすべてだったのが、コミュニケーションの世界が一気に広がる感覚がありました」
――堀江さんにとっては、アルバイトは大きな経験だったんですね。
「そうですね。いま声優になってみて、そのときのリアルな経験がお芝居の会話でもかなり大きな財産になっているんじゃないかと思うんですよね。会話の押し引き、言葉のニュアンス、距離感の掴み方、台本だけではわからない人と人のリアルなやりとりの空気感とか。前回もお話しましたが、中学~高校時代は友達もほぼいなかったので、余計に大学に入ってバイト先でのコミュニケーションが、僕にとっては大きかったのかもしれないです。振り返ってみると、その時に培った感覚がいま声優としての堀江瞬を形成しているんだろうな、って思いますね」
■「あれ、いま俺セリフしゃべったっけ?」

――堀江さんにとって、転機になった作品というと?
「そうですね。転機というといくつか思い浮かぶ作品があるんですが、『お芝居に対する捉え方が変わった』という意味でいうと『さらざんまい』という作品で陣内 燕太役を務めた経験が大きかった気がします。先ほど『アルバイトでコミュニケーションの会話を学んだ』とは言いましたが、それはあくまで『いま振り返ってみると......』という話であって、当時はまだ新人でそんなことを意識してお芝居で表現として出すことすら、できていなかったんです。なんなら、それが『できていない』ということすら、まだ自分では自覚できていない状態に近い」
――「何がわからないかが、わからない」という状態に近かったんですね。
「台本は『あらかじめこういうことを話す』というのが決まっているけど、本来は、会話って相手の言葉を受けて、自分の発する言葉が変化していくものじゃないですか。当時は、それがわからなくてあらかじめ『こう言おう』と用意していったセリフを、まるで自分の手札から決めたカードを切るかのように、やっていた。......だったんですけど、村瀬歩さん演じる一稀や、内山昂輝さん演じる悠と会話していると『こう言われたから、こう返そう』と、相手の言い方によって自分のセリフの言い方も変えるのが自然とできたんですよね」
――何か、きっかけとなる出来事があったりしたんでしょうか?
「いや、それが自分では『これ』というきっかけらしい出来事があった気はしていなくて、本当に不意にっていう感じなんですよね。しいて言えば、僕の立ち位置が主人公キャラクターの中でも3番手的な立ち位置でセリフ量は多いけど比較的気負わずに収録にのぞめた、その主人公3人での掛け合いがたくさんあったというのが大きかったのかもしれないです。それまでも主人公は何作かでやる機会をいただいていましたが、新人というのもあって変にプレッシャーを感じる現場も多くて。緊張しすぎて、『心で会話する』ということまでまだ意識ができていなかったんだと思います」
――じゃあ、堀江さんとして自然体でアフレコにのぞめたのがよかった?
「そうなのかもしれないです。それで思い出したんですけど『さらざんまい』を収録する中で一度、自然とセリフが出てキャラクターとシンクロした感覚になった瞬間があって。『あれ、いま俺セリフしゃべったっけ?』と、自分でもしゃべったのかどうかわからなくなるような感覚になったことがありました」
――そんなことがあるんですね......!
「そんな経験も含めて、『心で会話する』という感覚を掴み始めたのが『さらざんまい』だったんだと思います。それまでも一生懸命、全力で取り組んではいたけど、振り返ってみると『人の言葉を聞こう』という意識があまりなかったので、やっぱりそれだと上辺の部分しか表現できていなかったのかなって。その現場以降、人の言葉を聞いて生の会話をしようという意識はものすごく強くなりました。ただ、キャラクターと心がぴったりと重なる感覚になったのは、後にも先にもあの一度きりなんですよね。また、あの感覚でお芝居がしてみたい。もしかしたらそのときの感覚を、いまでも追い求めているのかもしれないです」
■「心で会話する」ことを大切にする意味

――先ほどから、何度か「心で会話する」という言葉が出てきているんですが、それって堀江さんのどんな気持ちから出てきているんでしょうか?
「日常生活だと、ふつう僕たちはみんな当たり前のようにできていることだと思うんですよ。ふだん会話をするのに、練習していく人っていないじゃないですか?用意した言葉を言うのは、会話じゃなくてスピーチになってしまう。いまこうしてインタビューで話しているときも、ライターさんが僕の話をもとに質問を考えて、その質問を受けて僕が答えている。事前の質問ももらってますけど、会話の流れ次第で質問も、答えも流動的に変わっていってるじゃないですか。それって、この場で『お互いの心によって会話が決まっていく』ことだと思うんですよね」
――なるほど。ちゃんと一つひとつの言葉が、自分から出てきて生まれていく感覚ですね。
「そう、でも僕たち声優の仕事は逆で、『言うべきこと』がセリフとして決まっている。その言うべきことが決まっている状態に対して、どうすれば心を入れたセリフに聞こえるのか、を考えなければいけないんですよね。新人の頃はそれがわからず、セリフを何度も家で練習して、キーや喋り方を調整しながら『そのセリフの正解』を探っていました。でも、それだと相手の言葉によって自分の言葉が変化しなくなってしまう。『心で会話している』ということにはならないような気がするんです。なんなら昔は、喧嘩してるシーンも家でめちゃくちゃ練習していました。喧嘩なんてとくに相手がどのくらい激昂しているかで、こちらの言い方は変わるのに(笑)」
――たしかに(笑)。前回のインタビューで、養成所時代に「型がある人ほど苦戦していた」というお話にも通じている気がします。
「あぁ、もしかするとそういう部分もあるのかもしれないですね。それに、僕は不器用なので一度セリフの言い方を固めてしまうと、現場で『違う』と言われたときに即座に対応できなくなってしまう、という側面もありました。現場でちゃんと柔軟に対応できるようにするためにも『言い方は決めすぎないほうがいい』。そして、相手の言葉をちゃんと聴いて自分のセリフを発するようになったのかな、って」
――心で会話することが、よりリアルにキャラクターの感情を描くことにつながるんですね。そして、その学びがカラオケのアルバイトにあった。
「そう、いま振り返るとカラオケ店でのバイト経験に、そのヒントがたくさんあったんだなって思うんです。それこそ仲間と語る楽しさもそうですけど、接客する上で、それまで学校や家庭で通用していたことが通用しないもどかしさだったり、店員としてお客さんに接することだったり、初めて親や先生以外の大人とやりとりする経験だったり。そういうあらゆるやりとりの中で、自分自身が感じたものがそのまま、お芝居で表現したいことの原石になる。そういう意味では、お芝居をする上で必要なことや、演じ方のヒントはリアルな実世界の中にたくさんあるのかもしれません」
■作画クオリティに負けないお芝居を|「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」アルベルト
 (C)謙虚なサークル・講談社/「第七王子」製作委員会
(C)謙虚なサークル・講談社/「第七王子」製作委員会
――2025年7月から第2期が放送されている「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」では、主人公・ロイドのお兄さんで第二王子のアルベルトを演じられています。堀江さんから見たアルベルトは、どんなお兄さんですか?
「なかなか変わり者のキャラクターが多いの中では、アルベルトは正統派で圧倒的なお兄ちゃんっていう感じがしますよね。かなりの弟思いな感じは第1期のときから感じてもらえていたと思いますが、じつは第2期でもそれが結構出ていて。本当に頼り甲斐があって、頼もしいところが魅力的なキャラクターだと思います。弟との仲が良くない僕からすれば、全然、弟に対する愛情のかけ方は共感できなかったけど(笑)」
――堀江さんから見て『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』はどんな魅力がある作品だと思いますか?
「これは第1期の頃から出演している声優陣、みんなが感じていることだと思うんですが、あまりにも絵がきれいすぎると思うんです。観ている方の反応を見てても、『キャラかわいい』『ストーリーが面白い』とかはもちろんあるけど『絵がきれい......なんだこのクオリティは...!』っていう声が一番、際立っているんですよね」
――たしかに! 個人的には、第1話の前半でロイドとシルファが剣術の稽古をしているシーンで、すでに「何、この作画......!」と感じていました。
「いや、本当そうなんですよね。それでしかも、制作会社の『つむぎ秋田アニメLab』さんが初めて手がけるアニメ作品だというから、また驚きで......。戦闘シーンはもちろんですし、それ以外のシーンでも背景や演出にこだわりがいっぱい詰まっていて、映像のクオリティが高い。観ているだけでも楽しめちゃうんですよね。でも、その『観ているだけで楽しい』というのが、じつは役者にとっては悔しくもあるんです」
――というのは?
「それはやっぱり、『絵がすごい!』という反応がたくさん来たら、『俺たちのお芝居はどうなんや!』という気持ちになるじゃないですか(笑)。だから現場でそんな話をしたことはないけど、出演している声優たちはみんな、きっと『絵に負けない芝居をしなければ!』と考えてると思います。その作画クオリティに見合う、あるいはそれを凌駕するようなお芝居。少なくとも、僕はめちゃくちゃ意識しています!」

取材・文/郡司 しう 撮影/小川 伸晃