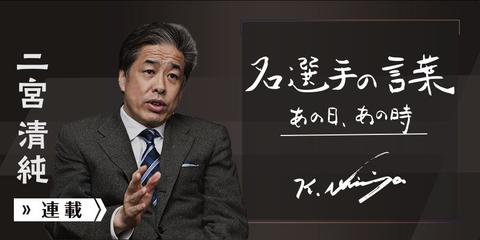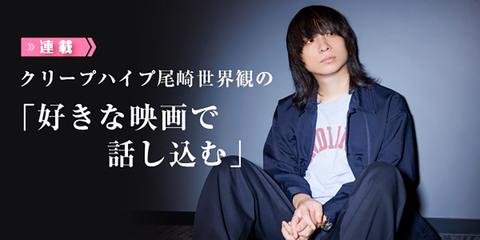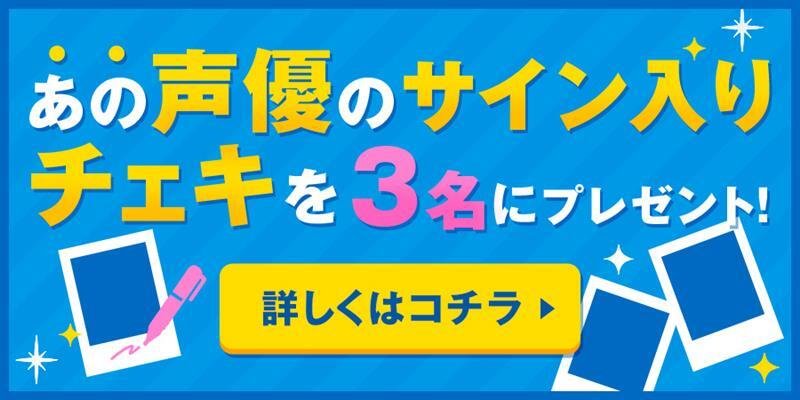声優・佐倉綾音インタビュー#2「『お芝居は仮想現実だと思う』生々しさとアニメ芝居のはざまで思うこと」
アニメ 見放題インタビュー
2025.07.04
「僕のヒーローアカデミア」の麗日お茶子をはじめ、「五等分の花嫁」の中野四葉、「SPY×FAMILY」のフィオナ・フロスト、「SAKAMOTO DAYS」の陸少糖(ルー・シャオタン)など、数々の人気作品で主要キャラを好演する、声優・佐倉綾音さん。人間に対する深い洞察から生まれるその演技力と、そのキャラの気持ちや感情を真っ直ぐに伝える表現力は、アニメファンならずとも心を打たれます。2025年4月にはTBSラジオでレギュラー番組がスタート、豊かな語彙と軽妙な毒を散りばめたトークでラジオパーソナリティとしての才も発揮。活躍の場がさらに広がりました。この企画では全3回にわたり、佐倉綾音さんへインタビュー。ラジオへの思いやこれまでの歩み、お芝居に対する考えをひもときつつ、その人となりに迫ります。
■幼稚園に上がる前に、一度声優を諦める

――前回は、ラジオを中心にお話を伺ってきましたが、今回は「声優を志したきっかけ」をテーマにお話をお聞きしたいと思います。声優という職業を初めて意識したのはいつ頃だったのでしょうか?
「初めて『声優という職業があるぞ』と知ったのは意外と早くて......。たしか3歳くらいのときにはすでに、『ポケモンの主人公・サトシは、松本梨香さんという方が声をあてているんだよ』と親から聞かされて、声優の存在を知っていたと思います。それを聴いて『夢を壊された!』と失望するようなことはまったくなく、むしろ自分と地続きで生きている人間がそうやってアニメを作っているのはすごいことだ、と感じていました。そしてその頃、『私、声優になる!』と言い始めていたみたいです(笑)」
――この企画史上、最速ですね...!(笑)
「でも、根が引っ込み思案の恥ずかしがり屋なので、人前で何かを表現するのは大の苦手。親の前でごっこ遊びもできなかったくらいでした。あるとき、声優になると言っている私に、父が『いまこの場で「ポケモン、ゲットだぜ!」って言ってみな』と言ってきたんです。当然、恥ずかしいから『できない』と言うじゃないですか。そうしたらなんて言ったと思います!?『今ここでできないなら、声優にはなれない』と......(笑)」
――お父さん、めっちゃ厳しい......!(笑)
「ね。まだ幼稚園にも上がる前の子にそんなに求めます......?(笑)父はエンタメに対してアンテナが立っているタイプの人間だったので、今思うときっとそういうことも関係しているのかなとは思うのですが。そんな出来事があって『私、声優にはなれないんだ』と思い、それ以降しばらく声優という存在については忘れて生きていました」
――それが、どんないきさつでもう一度「声優になろう」と?
「小学校の頃、週6日、毎日なにかしらの習い事があったのですが、高学年になった頃に不登校になって、すべてがままならなくなってしまったんです。中学に上がってからは私自身がエンタメ、とくに実写作品に没頭して、その頃から『エンタメを作っている裏側の世界を見たい』と思い始めた」
――前回のお話でも、作品とセットで"裏側も知りたい"とおっしゃっていましたね。
「そう、多分、この頃からそんなふうに思うようになったのだと思います。でも当時は中学生。エンタメの裏側を見るためには『エキストラ、ひいては役者になるしかない!』と。でも『お芝居がやりたい』というわけでもなかったので、『とりあえずエキストラになって裏側が見れたらいいな』と思っていました」
■不登校だった自分が、養成所では皆勤賞

――最初は「エキストラになりたい」だったんですね。
「今でもそうなのですが、私、すごくせっかちで、『こう!』と決めたら思い立ってすぐに動かないと気が済まないタイプなんです。そのときもすぐ親に『この劇団に通ってみたい!』と打診をしました。両親も、『家に引きこもるよりも、外に出てくれるならそのほうがいい』と承諾してくれて。それにお芝居の勉強だけじゃなく、日本舞踊やボイストレーニングなど、いろいろなことが体験できる劇団でもあったので『体力づくりにもなるだろう』ということで、劇団に入れてもらいました」
――それで中学2年生のときに、「劇団東俳」に入ったんですね。
「そうです。劇団に入ってみたら、意外とお芝居をやること自体は、好きかもしれないと思えたんです。でも、どうやら私には自己顕示欲もなければ承認欲求もあまりない......。人に見られるのは恥ずかしいし、カメラを向けられるのも、ステージの上に立って人前でお芝居するのも、どうやら苦手。『そうじゃん。私、こういうの向いてないんだった。ここは私の居場所じゃないんだ』と思って。
そんなことを考えている頃、ボイトレの先生に『佐倉さんは声に特徴があって発声がしっかりしているから、声の仕事が向いていそうだね』と何気なく言われたことがあって、それが頭に残ったんです。考えてみたら、声優になればステージに立たなくていいし、顔を出さずともお芝居ができる。......当時の印象です(笑)。その辺りから『自分にはこっちのほうが向いているのかも』と思うようになってきました」
――改めて、声優の道に進むことを決めた瞬間ですね。
「ただ、声優への知識が『サトシ=松本梨香さん、ドラえもん=大山のぶ代さん』程度で止まっていたので、これは勉強せねば、と思って声優の養成所に入り直すことにしたんです。だから劇団東俳さんにいたのも本当、1年くらいのことで」
――1年......! 想像していたよりも全然短かったです。
「決断がわりと早い方なので、1年通ってみて『違うな』と感じたら、もう次の年には声優の養成所に入っていた、という感じでした。ただ、養成所といっても中学生から受け入れてくれるところがあまりなかったんです。かなり限られた選択肢の中で、ジュニアクラスがあるところを見つけてそこに入りました。ジュニアクラスということもあって、養成所時代に一度も、マイク前に立ってレッスンはできませんでした」
――そうだったんですか......! ちなみに養成所に入ってからのお芝居のレッスンは、佐倉さんにとってはいかがでしたか?
「劇団のお芝居と決定的に違ったのは、基本的な目線が台本にあること。でも、それさえできていれば、想像よりもずっと自由にお芝居ができるんだと感じて、とても楽しかった記憶があります。中学3年生のとき、不登校で学校には行っていなかった私ですが、養成所に関しては1日も休まず1年間通っていました」
――声のお芝居、というところが佐倉さんにとってぴたっとハマる感覚があったんでしょうか?
「そういう感覚も、確かにありました。自分の容姿にまったく自信がなかったので、『見た目を気にせずお芝居に集中できる』という安心感も大きかったのかなぁと思います」
■文字を生きた会話にすることの難しさ

――養成所時代に、何かお芝居のことで「自分にとって大きな学びになった」という出来事はありますか?
「学び......でもないかもしれないのですが、当時、声のお芝居を練習するときにマンガや小説を買って、セリフをお芝居で言いながら録音して、それを自分で聴く......みたいなことはしていましたね。そのときに『生きている人間の言葉って、文字になると急に再現性がなくなるのはなんでだろう?』と感じて、それがいまだにずっと気になっています」
――「再現性がなくなる」......? もう少し詳しくお聞きできますか?
「例えば、いまこうやって取材を受けて私が話す言葉も、撮影の合間に現場でしていた雑談も、そのまま文字に起こすとなんだか変な感じになるじゃないですか」
――それは僕もライターという職業柄、すごくよくわかります。喋ってるそのままを文字に起こすと語順もバラバラ、主語もないし、文の切れ目も全然わからなくなります。
「そうですよね......だけど、こうやって生きている人間同士が会話するとそれでも成立する。で、例えばその会話を録画・録音して見たとして、それは違和感なく見られるし、聴ける。生身の人間が話す言葉と、文字になって読むものは別なんです。それって逆にいうと、マンガや戯曲の脚本を生きた会話にするのって、すごく難しいことになるじゃないですか。 本来リアルであるはずの会話が、台本になった瞬間に、その会話の生々しさの再現性がまったくなくなってしまう」
――めちゃくちゃ面白い......! それが、養成所時代に自分で声のお芝居をしているときから、ずっと違和感としてある。
「そうなんです。だからセリフを見たときに『ふつう、こんな言い方しないよな』と当時から思っていました。例えば、『踊っているわ』というセリフを文字に起こすと"い"が入るけれど、喋るときには『踊ってるわ』と省略することが多いですよね。マダム的な人は『いるわ』と言うかもしれないですが(笑)」
――ライターで言えば「しかし」がそうです。原稿では見かけるけど、実際の会話ではほとんど登場しない(笑)。
「やっぱり!そういうのありますよね?(笑)この謎に私はずっと挑み続けている感覚なんです。そして研究し続けているのに、いまだに答えが出ない。逆に、『すごいな』と感じたコンテンツもあって。当時観ていた映画で、柳楽優弥さん主演で、デビュー作の『誰も知らない』という作品があるんです。たしかYOUさんが母親役をやられているのですが、その映画の会話を聴いていると『すごく生々しいまま収録されている』という感覚になるんです。しっかりとフィクションでありながら、半分ドキュメンタリーみたいな。初めて観たときにそれが衝撃で......『これがエンタメとして成立するなら、エンタメでできることって、まだまだあるはずだな』と。今でも本気でそう思います」
■現実にリンクする瞬間に、はっとしてもらいたい

――『誰も知らない』を観て、お芝居の奥深さに触れたわけですね。
「そうですね。ただ、どこまで行っても捉えられている気はしないですけど。お芝居って仮想現実だと思うんです。作品によって表現されている生々しさのパーセンテージは全然違っていて、それをどのくらいまで上げていくのか。今まで観てきたエンタメの中で、そのパーセンテージを限りなく上げたのが『誰も知らない』だったのだと思います。もちろん『誰も知らない』にも台本がある。自分も、台本があるなかで、どれだけそういう生々しい作品が作れるのかということは、昔からずっと考えています」
――なるほど......! 『誰も知らない』は、ある意味で佐倉さんにとってベンチマークみたいになっていて、佐倉さんのお芝居も「どれだけ生々しくできるか」を追求している感覚でしょうか?
「そうですね。ただ、それもある一方で、声優になってから一度ぶつかった大きな壁があって。それが、『アニメ芝居ができない』ということだったんです。"アニメ芝居"は言葉で説明するのが難しいのですが、簡単に言うと『現実でやったら不自然だけど、アニメの絵に合わせるとリアリティが出るお芝居』ですかね。それまでの私のお芝居は、『もしそのセリフを私が現実で言うとしたら、どう言うか』を意識した喋り方でしたが、『それだと、生々しすぎてアニメの絵には合わない』と当時のマネージャーから怒られてしまって。『頼むからアニメ芝居を覚えてくれ』と」
――確かに。『誰も知らない』とは真逆の方向性ですもんね。
「自分でも出演作を観ていて、『絵に合ってないな』と思うことは度々あって『これ、どうしたらいいんだろう』とは思っていたんです。マネージャーさんの言うとおり、『アニメの絵に合わせると自然になるお芝居』が存在しているのは頭ではわかっているけど、一方で『そんな人、現実では見たことない』と思って16〜17歳の頃は、かたくなにアニメ芝居をやるのを拒んでいました。でも、『そうしないとオーディションに受からないよ』とも言われてしまって。自分の理想のお芝居と、アニメ芝居の間には埋められない溝があって、けっして納得はできなかった。でも『覚えるしかない』と思って、アニメ芝居を体に叩き込んだ時期がありました」
――実際にそのお芝居を叩き込んでからは?
「そうすると、やっぱりオーディションにはすごく受かるようになるんですよね。だけど、自分としては腑に落ちていない感覚がずっと大きくて。『説得力は増したかもしれないけど悔しい』というのをずっと感じ続けているような気がします。未だに、自分はお芝居のことがなんにもわかっていなんだろうな」
――でも、先ほど佐倉さんが「仮想現実」という言葉を使っていて、それがまさにその通りなんだなと思いました。2次元と3次元の間を表現する。現実的すぎるのも違うし、虚構すぎるのも違う。
「そういう部分はあるかもしれないですね。途中から自分でも『ハイブリッドで行こう』と思うようになって。エンタメって基本的にはすべて虚構なので、その虚構の中で一瞬、現実にリンクするような感情が表現されたら、その瞬間、見る人は『はっ...!』となると思うんです。『なんでだろう、このセリフ急にやたら生々しい』みたいな。それで、台本を読んでいて『ここは生っぽさを入れてもいいかも』と感じたセリフをチェックしておいて、いざ現場でやってみたら、意外とすんなりOKをもらえたんですよね。そのとき、『こういうやり方なら表現できるんだ』と思って」
――すごい......同じキャラであってもずっと同じ表現でお芝居をしない。あえてポイントをつくることで、ふと現実に目が行くというか。
「たぶん、現実って多くの人にとってストレスでもあると思うんですよ。ずっと現実というストレスの中にいると、逆に集中力を欠いてしまうかもしれないから、虚構の世界が必要なんですよね。そして、逆に虚構の中にポツンと佇む現実的な瞬間があってもいい。その瞬間、『ストレスはあるけど、現実にまた向き合おう』と、皆さんの心を前向きにできたらいいなとは思います」
■「全部セリフっぽいほうがいいかも」|「ダンダダン」白鳥愛羅

(C)龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会
――「ダンダダン」では、モモやオカルンたちと同じ高校に通い、アクロバティックさらさらの能力に目覚める美少女、白鳥愛羅(以下、アイラ)役を演じられています。演じるにあたって、どんなことを意識していましたか?
「マンガや小説を読む時って、自分の中で誰かの声で再生されることが多いじゃないですか。でも私、『ダンダダン』の原作を読んだときは、登場人物の声がまったくどんな声でも再生されなくて、ただただ龍幸伸先生の絵力に圧倒されてしまったんです。『声が入り込むスキがない』というか。アイラに関してもそれが当てはまって、どういう声で喋ったらいいのか全然わからなかった。なんなら私としては『喋ってほしくない』くらいの感覚がありました」

(C)龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会
――じゃあ結構、アイラのお芝居を見つけるまでは難しかったんですね。
「難しかったですね。とくにオーディションのときには、アクロバティックさらさらを内包したときのアイラのお芝居も一緒にやらなくちゃいけなかったんですよね。オーディション用の台本の中に、ちゃんと『アクさらアイラ』のシーンが入っていて。元々のアイラの声も想像できていないものだから、かなり手探りで提出したような覚えがあります」
――実際に現場に入ってからはいかがでしたか?
「それが、原作を読んでいる段階ではあんなに想像ができなかったのに、現場に入ってモモ役の若山詩音ちゃんと、オカルン役の花江夏樹さんお二人のお芝居を聴いたときに、『あっ、あの二人ってこういう声だったんだ!』とめちゃくちゃ腑に落ちたんですよ。その説得力のあるお芝居にとても助けられて、『この二人がそういう表現なら、アイラはもう少し毛色が違ってもよさそう』と思えました。アイラは自分のことを"美少女"と自称してはばからず、その立ち振る舞いもちょっと現実離れしたところがあるので、『全部セリフっぽいほうがいいかも』と思って」
――たしかに!「周りから自分はこう見えてる」というのが見えた上で振る舞っている感じのキャラだったので、すごく納得感があります。
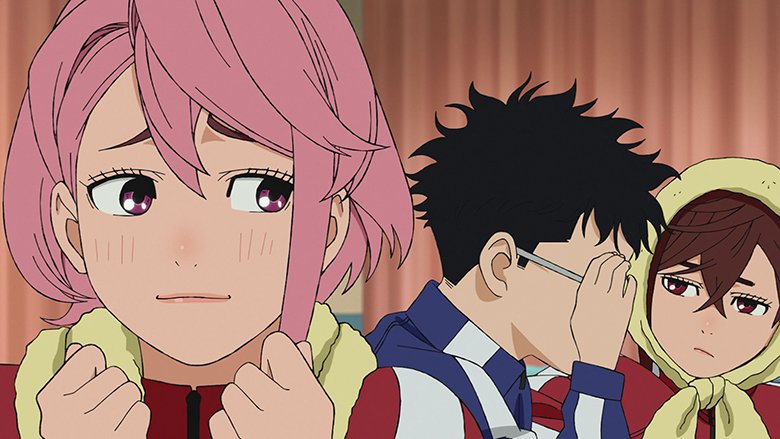
(C)龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会
「彼女の中で、脚本とセリフが存在しているような喋り方。でも彼女自身の感情や心が見えた瞬間に、そこから解き放たれた声を出す。『私なら、そんなアイラが聞きたいかも』と思って、彼女を演じるときに意識していました」
――佐倉さんから見た、アイラの魅力ってどんなところでしょうか?
「登場したとき、アクロバティックさらさらとの戦い、それ以降とで、彼女の印象ってガラリと変わるじゃないですか。そういう多面的な人間性を持っているのは、彼女の大きな魅力の一つだと思います。現実にいたら、ちょっとヤバめな人かもしれないけど(笑)。『ダンダダン』は作品として、『ありえないことが起こる』ファンタジーの要素がすごく大きいので、振り切った『ありえない立ち振る舞い』が成立しやすい。そんな姿を見せてくれるのも、彼女の魅力の一つかなと思います」
■現場でも話題騒然だったアクさら回|「ダンダダン」白鳥愛羅

(C)龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会
――2025年7月からは、待望の第2期が始まります。第1期を振り返ってみて、佐倉さんの注目シーンをお聞き......っていうかもう、あのアクロバティックさらさらの回ですよね。あのときのお話をお聞きしたいです(笑)。
「(笑)。あの回は、最初に台本を読んだ段階からすでに泣いてしまっていたんですけど、結構キャスト陣のグループLINEでも話題沸騰で、『台本読んだ?泣ける』『俺も泣いた』なんて、そんな言葉がアフレコ前から飛び交ってました。いざアフレコに入ったら、私もまたその映像を観て泣いてしまって......というか現場でもみんな泣いていました」
――制作スタッフやキャストのあいだでも印象的な回だったんですね。
「そうですね。取材もあるので、放送よりも前に完成した映像も観ていたのですが、家で観ていて本当に何が起こっているのかわからなかったぐらい、心に大きく響いてくる仕上がりになっていて......それ以前のお話までと、全然雰囲気も違うし『スタッフさんが、すごい方向に舵を切り始めたぞ』と思ったくらいです。『この回に反響がなかったら、嘘だ』とも思ったし、私自身、それほどまでに衝撃を受けた回でした。実際に放送されてちゃんと反響があって、正当な評価をいただいて、とてもホッとしました」
――そのときのアフレコ現場での思い出などはありますか?
「現場で泣いてはいたものの、私はその後のシーンでアクさらを内包したアイラも演じないといけなかったので、アクさらを演じる井上喜久子さんのお芝居も観察しなきゃいけなかったんです。

(C)龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会
喜久子さんのお芝居を観て、『このキャラがアイラの中に入ったら、どう演じればいいか』の戦略を立てようと思っていたのですが、喜久子さんを見ていたら『あれ?』と思って。私がテープオーディションのときにやっていたお芝居と、喜久子さんのお芝居にあまり相違がない。『私の思い描いていたアクさらのお芝居が、そのまま喜久子さんのアクさらで再現されている!』と思って、とてもびっくりしました」
――そんなことあるんですね......!
「役者って、ちょっと変わった視点を持っている方も多いので、ほかの方のお芝居を見て『その発想はなかった!』と思うことだってたくさんある。そんな中で、たまたま喜久子さんのお芝居と私のお芝居の『向かって行きたい方向が一緒だった』ということが、とても嬉しくて。それのおかげでアクさらを内包してからのアイラのお芝居も、迷いなくのぞむことができた気がします」
――確かに、観ている私たちも「アイラの中にアクさらがいる」ことが違和感なく、すんなりと受け入れられた気がします。最後に、佐倉さんから見た「ダンダダン」の作品の魅力をお聞きできますか?
「初めて原作を読んだときに、『これをアニメにするのは大変だろうなぁ』と、少し不安な気持ちになったんですよ。龍先生が命を削って描いていらっしゃるような作品で、先生の絵だからこその躍動があるし、それに読者として揺さぶられる感覚がありました。私、エンタメの中でもマンガが一番、総合芸術だと思っているんです。ふつうはいろいろな分担があって作品をつくるけど、マンガは監督、脚本、美術、役者をすべて一人で担っていますよね。あんな作品を、一人の人間が描いていると言うこと自体が、もうオカルトみたいな現象じゃないですか(笑)」
――たしかに!さすがの表現力です(笑)。
「アニメにするにあたってあの作品をどう分担して、どう再解釈・再構築していくんだろうと気になっていたんですけど......やっぱりサイエンスSARUさんって、本当、凄い方たちの集まりでしたね。映像などの表現力が突き抜けていて、本当にメディアミックスの方法としていろいろな人に観ていただきたい作品だなと思いました」
――「表現力が突き抜けている」っていうのも言い得て妙です(笑)。
「監督の思想がしっかりと入っているのもよくて、ただ忠実に映像化して『原作を再現しました』じゃないんですよね。もちろん原作の再現が大切な場合も多いですし、今はその方が主流でベターですが、『ダンダダン』はかなり大胆に、原作が再構築されている部分もあったりするので、挑戦や冒険をしているなと思います。常人離れしたアニメ化ですよね(笑)」

取材・文/郡司 しう 撮影/小川 伸晃