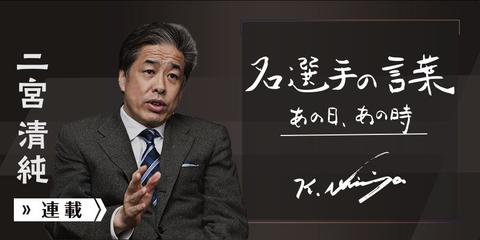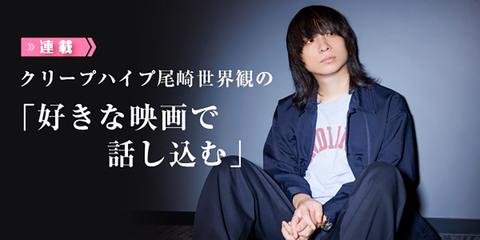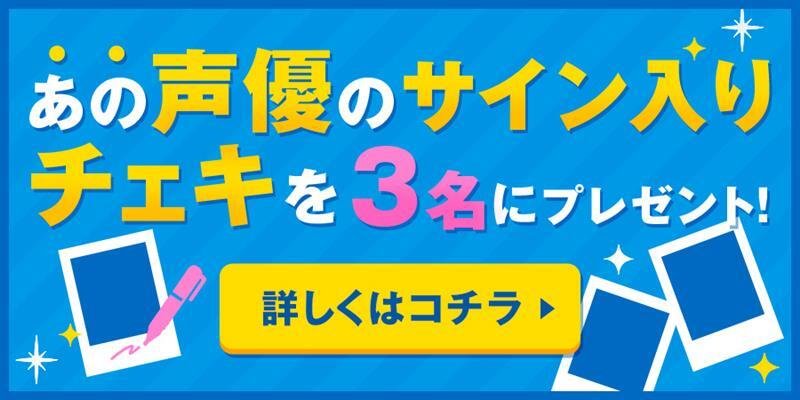声優・早見沙織インタビュー#2「客席からステージの上に届いてくるもの。私の歌を支える存在になっている」
アニメ 見放題インタビュー
2025.08.01
「SPY×FAMILY」のヨル・フォージャー役、「鬼滅の刃」の胡蝶しのぶ役、「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」のリュー・リオン役など、数々の人気キャラクターを演じ、その魅力を引き出してきた声優・早見沙織さん。歌手としての顔も持ち、2025年にはアーティスト活動10周年を迎えます。節目を迎えたいま、彼女はアーティストとしてどんな気持ちで音楽に向き合い、声優としてどんな気持ちで役に向き合っているのか。このインタビューでは全3回にわたって、早見沙織さんの音楽活動と声優の仕事に対する思い、そして人となりをひもといていきます。
■2021年、アーティスト活動にテーマを設定したワケ

――アーティストデビューしてからの10年間を振り返って、とくに印象的だったできごとはありますか?
「そうですね。たぶん場面ごとにはいろいろな大変なことってたくさん経験してきた気もしているんですが、過ぎてしまえば『喉元を過ぎれば......』という感じで、あまり自分としては苦労話みたいなものは少ない気がしているんです。
ただ、なかでも印象的だったのは、やっぱりコロナ禍での活動です。あのときは、みなさんも数ヶ月間にわたって家に引きこもらざるをえなかったと思いますが、私も音楽活動を含め、すべての活動をストップしなくてはいけなかった。そのときに自分の中から湧いてきた感情や、生まれた音楽、言葉っていうのは、その後のアーティスト活動にもすごく影響があったと思います」
――コロナ禍で、どんな思いが早見さんの中に生まれてきたんでしょうか?
「コロナ禍で、思うように人と会えない時間が長く続いたとき、やっぱり孤独だったんです。その孤独を感じたときに力になってくれるのが、音楽だった。でもよくよく考えればコロナ禍よりも前だって、自分が苦しいときとか、孤独を感じたときにはいつも音楽が私を救ってくれていた。自分の人生を振り返ると、いつでも音楽が支えてくれていたんだなって。
そしたらふと、そうやって私自身が音楽から受け取ってきたものを、今度は私が楽曲を作っていくなかで、聴いてくださる方々に返していけたらいいな、という思いが浮かんできた。そこで、私が音楽から受けとってきたもの、音楽を通じて表現したいことを明確にしようということで、活動テーマを決めることにしました」
――そのテーマが、「孤独や生きづらさを感じる人の心に寄り添い、光となる音楽を届ける」。
「そう、あらためてテーマとして言葉にしてみて、私自身、アーティスト活動を始めたときから、この思いがじつは根源的にはずっとあったということにも気づきました。それをコロナ禍のタイミングではっきりと言葉にしたことで、チームメンバーともより活動する上での気持ちが共有できるようになったし、聴いてくれる方にも思いが届きやすくなった。
『テーマを決める』って普通に考えたら範囲を限定してしまう気がしますが、実際にテーマを決めてみると、むしろそこから音楽活動にいろいろな広がりが生まれてきたんじゃないか、という気がします」
――テーマを定める前と後では、自分の中で音楽に対する思いというのは、かなり変わりましたか?
「そういうわけでもなくて、おそらく自分の中で音楽にかける思いっていうのは、10年間の中であまり変わっていないんですよ。むしろ今も10年前も同じだと思っていて。前回のインタビューで『10周年記念ライブ「HAYAPOP」では私の音楽の多面的な表情をお見せしたい』というお話をしましたが、じつをいうとそれもアーティスト活動を始めた頃からずっと考えていたこと。
2ndアルバム『JUNCTION』を作るときの打ち合わせでも『一人の人間の中にある、いろいろな側面を、一曲ごと別の角度からすくい上げていきたい』という話をチームにしていて、それが今回の10周年ライブのコンセプトにも繋がってきていたり」
――元々抱いていた思いが、テーマを定めたことでより輪郭がはっきりした、と。実際、テーマを定める前と後で、変化を感じる瞬間はありますか?
「いちばんは、やっぱり聴いてくださる方の反応です。『早見沙織は、そういうテーマで楽曲を作っているんだ』ということが伝わった上で聴いてくださるので、『これはそういう曲だったんだ』『この歌詞はそういう意味なんだ』みたいに、より曲から感じ取れるものが鮮明になったというお声をよくいただくようになりました。
元々、ジャンルレスで幅広い音楽をお届けしているので、その根底に私なりの音楽に対する考え方が共通しているということがわかっていただけるだけでも、やはりテーマを定めて明言したことには価値があったのかな、と思います」
■声優で役に向き合う経験が、歌にも生きている

――デビュー当時から「一人の人間が持つ多面的な部分を、楽曲ごとに表現したい」と感じていたというお話がありましたが、早見さんが声優として活動なさっていることにも関わりが深いように感じました。
「たしかに......いま、そうおっしゃっていただいて、そういう部分はあるかもしれないと思いました。声優が演じる役と出会うって、それこそ同じ人物、キャラクターって1人もいないんですよ。物語の立ち位置的に、似た感じのキャラクターはいるかもしれないけど、それでもみんなまったく違っていて。
声優としての活動を始めてからは、もうすぐ20周年になるんですが、その20年間の中で出会ってきた一人ひとりに、それぞれ個性や感情があるっていうことを、私は演じてきた役を通じて教えてもらった気がします。そして、無意識的にそんな思いが私の音楽活動にも反映されているのかも、と今日感じました」
――前回のインタビューで「HAYAPOP」への意気込みについて「会場にいる一人ひとりに向けて歌っていきたい」とおっしゃっていましたが、まさしくそんな経験から来るのかもしれないですね。
「声優として、いろいろなキャラクターに出会い、それぞれの違いを見てきたからこそ、いろいろな方の表情や人生が浮かぶようになったのかもしれないですね。とくに最近は、ライブでも客席で聴いてくれる方がいるっていうのが、すごく大きなことだなと感じるようになってきて。
レコーディングだと一人で部屋にこもって黙々と作業をしているだけ。でも、ライブになれば、目の前に笑顔があったり、ときには涙している方もいたりして、同じ歌を歌っていてもそれは表現の仕方が無意識で変わってくる部分があるのかなって思うんです」
――ライブでしか生まれない表現がある。
「そう、そしてそれがお客さんとのコミュニケーションから生まれる、ということですね。元々、私自身はどちらかといえば緊張しいで、会場が変わるたびにゼロから気持ちを作らなきゃいけなかったんですけど、最近はライブ中のお客さんとのコミュニケーションから、自分がたくさんのエネルギーをもらっているんだなって。私が歌を届けているつもりが、逆に客席からもらえるものが大きくて、それが自分の歌を支える力になっているというのは、すごく感じています」
――客席にいるお客さんから受け取っているものを、言葉にするなら、どんなものなんでしょうか?
「なんだろう。でも、感情......なのかな。私がライブに行って、音楽を聴く立場だったらやっぱり心が動いた瞬間に笑顔になったり、涙が出てきたり、『わーっ!』ってテンションが上がったりすると思うんです。
そういう感情が動いた瞬間を見て、人の心に触れたような感じがするのかな。それで私自身もステージの上から、一人ひとりの動きや表情を見て感情も動かされているんだと思います。だからなのかな......ここ最近のライブだと毎回と言っていいほど、私自身も感極まることが増えてきました」
――早見さんが感じる「歌がもつ魅力」をお聞きしてもいいですか?
「いろいろな魅力が思い浮かぶんですけど、一つは、時間を超えて届き続ける、ということ。懐かしいメロディーを聴いただけで、自分自身が何十年も前に感じた気持ちとか、場面とかをぱっと思い出せたりするじゃないですか。その瞬間はタイムトリップに近いと思うんですよね。
それか自分が知らない昔の曲だったとしても、聞けば当時の情景がなんとなく浮かんできたり。曲を通じて、数十年前の自分、あるいは他人と共感しあうっていうのは、歌だからできることなのかなって思います。もう一つは、言葉でお伝えするのが難しいんですけど、『言葉だけで届ける』のとは違う届き方をする、ということでしょうか」
――もう少し詳しくお聞きできますか?
「声優業にしても、ラジオ番組のパーソナリティにしても、私自身いわゆる『言葉を届ける』ということを日常的にやっていて、たとえ同じ言葉や文章だとしても、歌にのせて相手に伝えることで、受け取る印象とか起こる感情とかが変わってくるっていうのを、日々感じているんです。
ラジオ番組のスピンオフコンテンツで『声に出して聴きたいJ-POP』という朗読のコーナーをやっているときに、そのことをよく実感するんです。これがリスナーからのリクエスト曲の歌詞の一部を、BGMなしで朗読してみるというコーナーで、自分がよく聴いている曲であればあるほど、音楽なしでその言葉だけを聞くと全然言葉の味わいが違うんです。
例えば、それによって歌詞の意味が別の角度から見えてくることもあるし、すごく物悲しい言葉を明るい音楽に乗せることでマイルドになっていたんだ、ということもあるし」
――面白い......! そのアーティストがなにを届けたいのか、より深い部分で見えてきそうな試みですね。
「そういう見方も、全然できると思います。これは逆説的ではありますけど、言葉単体での届き方と、音楽に言葉を載せたときの届き方っていうのが全然違うということを、わかりやすく実感できる例だなって。ときにはそのコーナーに、私の曲が届くこともあったりするんですけど、自分の歌の歌詞を音楽なしで朗読する機会ってほとんどないので、歌詞だけで聞くとこんな印象になるんだ、と感じられるのは、自分の歌ながら新鮮な発見もあります。
そうやって考えたときに、『歌って、なんて深くて、いろいろな楽しみを秘めているんだろう』という気持ちになるんですよね。何度も聴いたり、歌詞だけ朗読してみたり。それだけリピートしても新しい発見があることが、歌の懐の深さや魅力なのではないかと感じています」

取材・文/郡司 しう 撮影/小川 伸晃