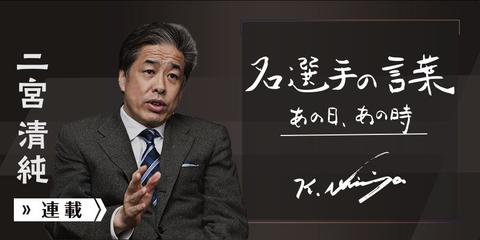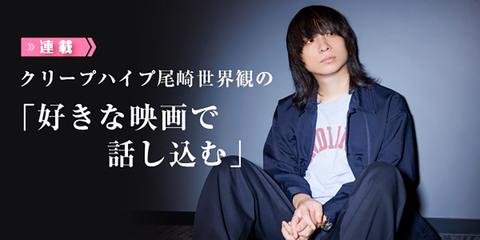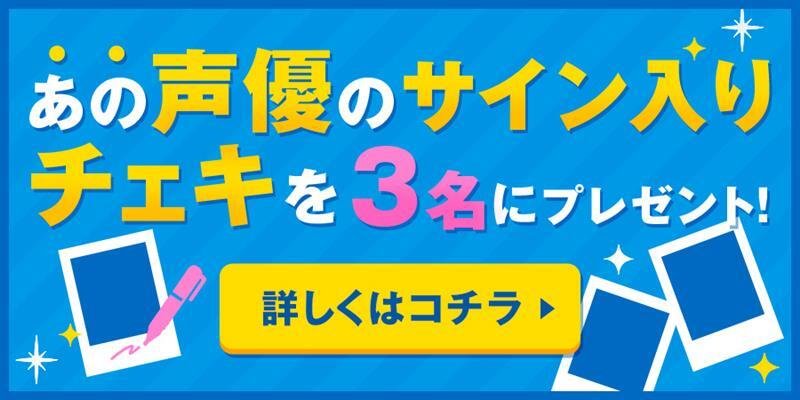国内外でさまざまな賞に輝いた傑作「おくりびと」に込められた視聴者への"問い"
映画 見放題
2024.10.15
第81回アカデミー賞外国語映画賞、第32回モントリオール世界映画祭グランプリ、第32回日本アカデミー賞最優秀作品賞、第33回報知映画賞作品賞など数々の賞に輝いた傑作、映画「おくりびと」(2008年)。
同作品は、遺体を棺に納める納棺師という職業を通して、さまざまな死と向き合い人生を見つめるヒューマンドラマ。元チェロ奏者の主人公が楽団の解散を機に、実家のある山形に戻り、そこで納棺師として働く姿を描く。
元チェロ奏者の大悟(本木雅弘)は、妻・美香(広末涼子)に「冠婚葬祭の仕事」とごまかし、納棺師の見習いとして働いていた。日々さまざまな死と向き合う中で、大悟は戸惑いながらも納棺師の意義ややりがい、すばらしさに気付いていく。そんな折、美香に仕事の内容がばれてしまい辞めるよう頼まれるが、それを固辞したことで、美香は家を出てしまう、というストーリー。
作品の中軸に「死」というテーマを据えながらも、夫婦の愛情と思いやり、親子の確執、納棺師という職業への偏見、さまざまな人間模様など、多面的なメッセージを含んでおり見応えがある。中でも、大悟と美香の関係性や、社長の佐々木(山崎努 ※崎は立つ崎)が語る死生観、大悟の父親とのエピソードなどは、物語の大きな柱として描かれ、見る者の心をわしづかみにする。
"死"を通して問いかける視聴者へのメッセージ
この作品のすばらしいところは、物語の奥に"視聴者への問いかけ"があるところだ。さまざまな死と向き合う大悟の目を通して、それぞれの遺族のバックボーンや事情を丁寧に描くことで、死者の死に至るまでの"生"にも思いを馳せてしまう構造となっており、見ていてふと自分の生き方について考えを巡らせてしまう。
また、佐々木が干し柿をクチャクチャと食べるシーンや、佐々木と大悟がフグの白子を吸うように食べるシーン、佐々木と大悟と事務員の百合子(余貴美子)がフライドチキンをしゃぶりつくように食べるシーンなど、あえて咀嚼するシーンを強調して、「生きるということは他の動物の死の上に成り立っている」ということを強いメッセージとして打ち出している。
日頃、つい目をそらしてしまうが、誰もが必ず迎える「死」について描くことで、反対側の「生」について立ち止まって考えさせるという狙いがあるのだ。
納棺の儀での本木の所作の荘厳さや、広末が表現した美香の夫に対する思いがあふれる瞬間、山崎演じる佐々木の飄々(ひょうひょう)とした雰囲気など、役者陣の演技の素晴らしさはもちろん、作品に込められた視聴者への"問い"にも向き合ってみてほしい。
文/原田健