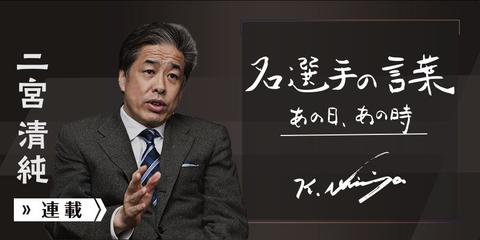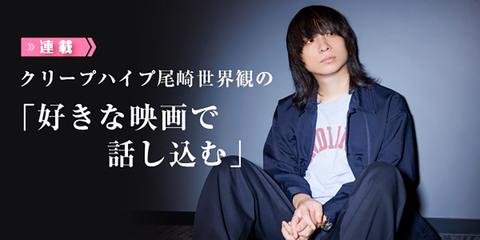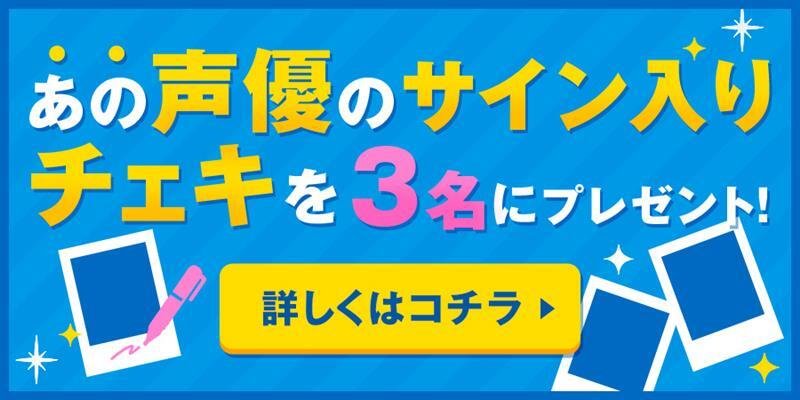「伝えたいのは心」八代目尾上菊五郎に聞く、歌舞伎の大名跡襲名後の現在地
エンタメ インタビュー
2025.10.22
5月に、歌舞伎界の大名跡を八代目として襲名した尾上菊五郎。屋号は、音羽屋(おとわや)。長男・六代目尾上菊之助との親子同時襲名に密着したドキュメンタリー番組『伝統と革新 蒼き想い~八代目尾上菊五郎 六代目尾上菊之助 重責と覚悟の120日~完全版』がJ:COM STREAMで10月1日より見放題で最速配信している。各地で続く襲名披露興行中の八代目尾上菊五郎に話を聞いた。いまの心境、演目の見どころ、歌舞伎への思いをお届けする。
■襲名披露興行を支える「想定外」
――ご襲名おめでとうございます。まずは襲名後のご感想をお聞かせください。
「神田明神ではZeebraさんにラップでお練りにお力添えいただき、手打ち式では先輩、同輩、後輩が並ぶ中、菊五郎としてのスタートを切らせていただきました。劇場では温かいご声援をいただき『八代目』と呼んでいただくたびに嬉しさで胸がいっぱいになります」
――ここまでのところ想定外もなく順調なようで、何よりです!
「どちらかと言えば、想定外ばかりでした(笑)。ただ何より想定以上だったのは、襲名に向けて皆さまが一つになり、大変力強く支えてくださったことです。日々の舞台も皆様のお力、そして一座全員の力で成り立っていますが、襲名では、歌舞伎界全体からのお力添えと祝福を感じました。感謝と同時に、受け継いだ名前の重みを感じています」

■道成寺の世界を親子で描く
――襲名披露興行は続きます。10月は御園座(名古屋)で、菊之助さんと親子で『二人道成寺』を。
「『道成寺(正式名:京鹿子娘道成寺)』は、音羽屋が大切にしてきた演目です。5月に歌舞伎座では、坂東玉三郎のおにいさん、菊之助、私の3人で踊らせていただきました。先輩方と舞台をともにすると、稽古以上の力が自然と出るものです。菊之助も、玉三郎のおにいさんとの舞台でそれを実感したはずです。それを熟成し、次の舞台に活かしてほしいです。彼はここ数か月で背も伸びました。身体が変われば、前回の感覚は通用しなくなりますので、またゼロから稽古をしてまいります。
ただ、前回の感覚をふまえ、毎日毎月ゼロからのつもりで役と向き合うのは、子どもに限った話ではありません。400年の伝統の中、先人たちは常にそのブラッシュアップを重ねてきました。だから同じ演目、同じ俳優でも、何度でもお楽しみいただける。そこが、古典歌舞伎の面白いところです」
――菊五郎さんご自身にとっては、5月の『道成寺』はいかがでしたか?
「15歳で祖父(七世尾上梅幸)と父(七代目尾上菊五郎)と踊った『三人道成寺』をふり返りました。私にとって初めての『道成寺』であり、心身ともに、ついていくのもやっとでしたが、今振り返ると、あの『三人道成寺』をもって、"自分は歌舞伎の家に生まれたんだ"と実感した気がします。歌舞伎役者として、歌舞伎の中で生かされていくんだと自覚した時でした」
――15歳の『道成寺』が、ある意味のスタートラインであり、この5月は、原点回帰のような『道成寺』に。
「倅は今11歳。彼もいつか今を振り返り、彼なりに気づくことがあるかもしれませんね。彼は芝居が好きで、ふたりの祖父、七代目尾上菊五郎と二世中村吉右衛門に憧れを持ちつづけています。向上心もあり、舞台後は自ら私に助言を求め、彼なりに咀嚼しながら挑戦し続けています。その姿勢に、つい高い要求もしてしまうのですが、彼はそれにも耐えてくれる。私が詰め込みすぎないよう、気分転換もしながら向き合っていかなくてはいけませんよね」
――10月は、河竹黙阿弥の世話物『鼠小僧次郎吉』も上演されます。
「五世菊五郎が、当時数えで14歳で蜆売りの三吉を演じて以来、代々の菊五郎ゆかりの演目です。江戸時代、人々は前世からの因縁や因果を深く受け止めていました。また、人を思いやる心も今以上に大切にしていました。その精神が『鼠小僧』には凝縮していると感じます。明治時代に書かれた作品でありながら、それでもなお"江戸の心を残そう"と、黙阿弥さんはこの作品を創られたのではないでしょうか。お芝居を通し、先人たちが大事にした"心"をお伝えしたいです」

■襲名披露興行、12月は京都南座へ
――襲名披露興行は、12月京都南座『吉例顔見世興行』へ続きます。『鷺娘』と『弁天娘女男白浪』と、こちらも人気演目が並びます。
「『鷺娘』は悲恋の踊りです。白無垢で始まり華やかな娘の踊りが続きますが、最後は地獄の業火に焼かれて息絶えていく。そのストーリー性も歌詞も曲も素晴らしく、早替りなど歌舞伎らしい視覚変化もお楽しみいただきたいです」
――映画『国宝』にも登場した作品ですね。
「そこも少しだけ意識しました(笑)。ですが、何より音羽屋ゆかりの舞踊です。九世市川團十郎さんが改良し、六世菊五郎が踊り込んで今の形に磨き上げました。六世は、伝説的なバレリーナ、アンナ・パブロワの来日公演で『瀕死の白鳥』に感銘を受けたそうです。終演後、彼女に、幕が降り白鳥が息絶える時の気持ちを尋ね、彼女は"そのまま舞台上で死んでも構わないと思っている"と答えたそうです。六世も"その気持ちが分かる"と握手をかわしたと。芸の最高峰では、国も文化も越えて心が通じ合うものなのですね。踊りとともに、作品の歴史にも触れていただけますと幸いです」
――そして音羽屋の代名詞とも言える世話物、『弁天娘女男白浪』です。
「私が京都で弁天小僧を演じるのは、菊之助襲名以来30年ぶりです。あっという間に、30年という驚くべき時間が経っていたのか......と。こちらも代々の菊五郎が大切にしてきた役です。ぜひ皆様、ご覧ください」

■ あの「こだわり」の正体は
――ところで菊五郎さんは、プライベートで何か「こだわり」はありますか?
「あえて言うなら、毎朝のコーヒーでしょうか。自分で豆を挽きハンドドリップで淹れています。お湯を注ぎ蒸らす時間も、その香りに心が落ち着くんですよね」
――番組では、日本舞踊の家元の尾上菊之丞さん、俳優で立師の山崎咲十郎さん、大道具の山中隆成さんのインタビューも。菊五郎さんは、丁寧にこだわりを持ち芝居作りをされる方なのかな、と想像しましたが、ご自身ではどのように思われますか?
「歌舞伎は、俳優の技芸だけでなく、衣裳・道具・音楽を含めた総合芸術。江戸時代に先人たちが、思いを込めて創った高いレベルのものに、一歩でも近づけるよう、皆で創り上げています。ただ、演じる俳優も時代も移り変わりますから、資料や文献をもとに、単に真似て再現するだけでは、別物ができあがってしまいます。大切なのは、先人たちの思い。それをお客様にどうお伝えするかを考えています。舞踊も殺陣も美術も、それぞれに試行錯誤します。その過程が"こだわり"と見えることもあるかもしれませんが(笑)、私にとっては先人たちへの"敬意"だと考えています」
――伝統と革新。今の時点でその手ごたえは?
「これからも古典歌舞伎、復活狂言(上演が途絶えた作品の復活)に取り組んでまいります。そして次の新作歌舞伎の構想も進めながら、菊五郎家の芸『新古演劇十種』の復活に向き合っていきます。コロナ禍以降、海外公演が難しいのが残念ですが、戦後間もない頃から、先人たちは、歌舞伎を通して世界と心をつないできました。創作者同士の交流も、世界のお客様に生の舞台に触れていただくことも、大切な文化交流ですよね。歴代菊五郎の功績をふり返り、自分がすべきこと、できることを一つずつ形にしていきたいです」
――最後に、読者の方へメッセージをお願いします。
「襲名披露興行は、来年6月の博多座まで続きます。八代目菊五郎・五代目菊之助として音羽屋の芸を懸命に勤めます。ぜひ劇場にお越しいただき、成長を見守っていただきたいです」

文/塚田史香 撮影/中川容邦